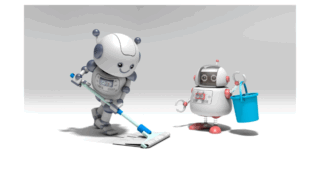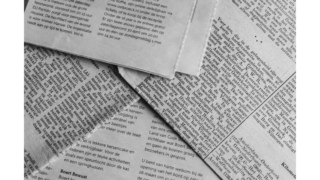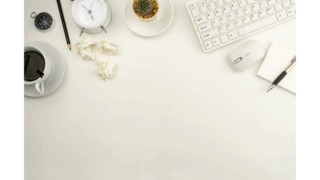介護タクシーの配車アプリには「よぶぞー」と「i-CareGO 結」があり、これらのアプリを利用することで個人や家族が手軽に介護タクシーを予約できます。
おすすめの介護タクシー配車アプリ
よぶぞー
「よぶぞー」は、個人や家族がスマートフォンから介護タクシーを予約できるアプリです。関東近郊(東京、神奈川、埼玉、千葉)や大阪、兵庫を中心にサービスを提供しており、車椅子利用などの条件や行き先をアプリで簡単に指定できます。過去の利用履歴に基づいて、乗降場所や運賃、介護サービスの内容を理解した上で安心して依頼できるのが特徴です。
このアプリは2025年8月15日には会員数が10,000人を突破したと発表されており、提携する介護タクシー事業者も順次追加されています。介護タクシードライバー向けの専用アプリ「よぶぞーPLUS」もあり、配車依頼の通知を受け取ったり、既存顧客からの指名予約を受け付けたりすることも可能です。
i-CareGO 結(アイ・ケアゴー)
「i-CareGO 結」は、株式会社アイネットがリリースした個人・家族向けの介護タクシー配車サービスアプリです。病院や介護施設を通さずに、利用者本人やその家族が直接介護タクシー事業者へ依頼や予約ができます。通院、買い物、旅行、冠婚葬祭など、様々なシーンでの利用に対応しています。
このアプリは、配車依頼に対して提携する介護タクシー事業者に一斉に依頼を送信し、複数の事業者から概算見積もりを受け取って比較・選択できる点が便利です。これにより、これまで複数の会社に電話をかけていた手間を大幅に削減し、迅速に介護タクシーを見つけられるようになります。NPO法人横浜移動サービス協議会が株式会社アイネットに依頼して、個人向けにカスタマイズされたサービスです。
「i-CareGO 結」のアプリダウンロードは無料です。利用者の介護の必要度などの情報は一度入力すればアプリに自動的に記録され、乗車地や目的地に関する詳細情報も入力できるため、より適切なサービスを依頼できます。
介護タクシーは、体が不自由な方が外出する際に非常に役立つ移動手段です。主に以下のような状況で利用されています。
どういう時に介護タクシーを使えばいいの?
通院や医療機関の受診
介護タクシーは、病院への通院、リハビリテーション、健康診断などの際に多く利用されます。公共交通機関の利用が困難な方でも、自宅から病院までスムーズに移動でき、必要な場合は乗降介助も受けられます。
具体的なサービス内容
出発時: 自宅まで迎えに来てくれ、着替えなどの外出準備や、室内からタクシーまでの移動、乗車の介助をしてくれます。
目的地到着時: 降車の介助だけでなく、病院の受付、会計、薬の受け取りなどもサポートしてくれます。
帰宅時: 病院からタクシーまでの移動と乗車の介助を行い、必要であれば自宅に入ってからの簡単な介助も含まれます。
日常生活に必要な外出
買い物: 日常生活に必要なものの買い物で、車いすや歩行器を使っている方にとって、介護タクシーは大変便利です。
行政・公共機関での手続き: 役所での手続きや選挙の投票など、本人が行かなければならない場合に利用できます。
金融機関での手続き: 銀行での預貯金の引き出しや振り込みなど、本人が対応する必要がある場合に利用されます。
補装具の調整: 補聴器、眼鏡、義足などの補装具の調整や購入など、本人が立ち会う必要がある場合にも利用可能です。
介護保険適用と適用外
介護タクシーには、介護保険が適用される場合と適用されない場合があります。目的や状況によってどちらを利用するかが変わってきます。
介護保険適用の場合: 正式には「通院等乗降介助」と呼ばれ、訪問介護サービスの一つで、日常生活や社会生活に必要な外出に限定されます。
特徴: 運転手が介護職員初任者研修などの介護資格を持っており、乗降介助だけでなく、病院での受付、会計、薬の受け取りなどの介助もしてくれます。車いすやストレッチャーのまま乗車できる車両が利用されます。
利用条件: 要介護1以上の認定を受けている方が対象で、ケアマネジャーが作成するケアプランに利用が組み込まれている必要があります。
利用目的: 主に通院、補装具の調整、金融機関での手続き、選挙投票、公共機関での申請など、日常生活や社会生活に必要な外出に限られます。仕事や趣味、レジャーなどでの利用はできません。
料金: 介護保険が適用されるため、原則1割(所得により異なる)の自己負担で利用できますが、タクシーの運賃や介護機器の使用料は保険適用外です。また、移動と介助がセットになっており、移動だけの利用はできません。家族の同乗は原則できませんが、特別な事情がある場合は自治体の判断で認められることがあります。
介護保険適用外の場合: 介護保険が適用されない場合でも、全額自己負担でタクシーとして利用できます。この場合、利用目的の制限は特になく、買い物、趣味、旅行など、幅広い用途で利用可能です。運転手が介護資格を持っているとは限らないため、介助が必要な場合は事前に確認し、必要であればご家族などが同乗してサポートすることもあります。
これは一般的なタクシーに車いす用のスロープやリフトなどの設備がついたものです。
特徴: 運転手が介護資格を持っているとは限らず、身体的な介助は原則行われませんが、事業者によっては介護資格を持つドライバーが介助サービスを提供している場合もあります。車いすやストレッチャーのまま乗車できる車両が使用されます。
利用条件: 要介護認定を受けていない方や要支援の方でも利用でき、利用条件は特にありません。身体の不自由な方や病気・ケガをされた方ならどなたでも利用可能です。
利用目的: 通院以外の目的でも利用でき、買い物、趣味、家族との外出、旅行など、幅広いニーズに対応できます。
料金: 介護保険が適用されないため、介助料を含め料金は全額自己負担となります。多くの自治体で福祉タクシー券の交付や運賃の一部助成などの制度がありますので、お住まいの自治体に確認してみると良いでしょう。家族の同乗も可能です。
緊急時や特別な配慮が必要な時
緊急時: 具合が悪くて救急車を呼ぶほどではないが、歩いて病院に行くのがつらい場合などにも利用できます。
車いすでの移動: リフトやスロープ付きの専用車両があるため、車いすに乗ったまま乗り降りでき、移動がスムーズです。
寝たきりの方: ストレッチャーに乗ったまま移動できる「寝台車」を用意している事業者もあります。
このように、介護タクシーは、体の不自由な方が安心して外出するための強力な味方です。利用を検討される際は、ご自身の状況や目的に合わせて、適切なサービスを選ぶことが大切です。
利用までの流れ
介護保険適用タクシーを利用する場合は、まず担当のケアマネジャーに相談し、ケアプランに組み込んでもらう必要があります。利用目的や頻度を具体的に伝えるとスムーズです。保険適用外のタクシーは、一般的なタクシーと同様に直接事業者に連絡して予約できます。
利用の際のポイント
目的の明確化: どのような目的で利用したいのか、どのような介助が必要なのかを明確にしましょう。
料金の確認: 事前に見積もりを取り、料金体系が明確な事業者を選びましょう。
予約: 特に介護保険適用タクシーは急な予定変更に対応が難しい場合や、予約が取りにくい場合があります。余裕を持って予約することが重要です。
自治体の助成制度: 自治体によっては介護タクシーや福祉タクシーの利用に助成制度がある場合があります。福祉タクシー券の交付など、お住まいの自治体に確認してみることをお勧めします。
介護タクシーの料金は、運賃、介助料金、介護機器の使用料金の3つの要素で構成されており、介護保険が適用されるかどうかで大きく変わってきます。
介護保険が適用される場合
介護保険適用の場合の介助料金は、原則1割の自己負担で利用できます(所得により2~3割)。これは移動と介助がセットになったサービスなので、介助が必要不可欠な場合に適用されます。
運賃と介護機器の使用料金は介護保険の適用外で、全額自己負担となります。
介護保険が適用されない場合
「福祉タクシー」や「介護保険適用外の介護タクシー」では、すべての費用が自己負担となります。
通常のタクシーと同様に、距離や時間に応じた運賃体系が一般的です。
初乗り運賃: 2kmまでで800円~1,000円程度。それ以降は、距離や時間に応じて加算されます。時間制運賃: 長時間の利用や待機が予想される場合に選択できます。事業所によっては、初乗30分で3,150円などの体系もあります。
乗降介助や室内介助、付き添い介助など、介助内容に応じて費用が発生します。
基本介助料: 無料~1,500円程度。
室内介助料: 500円~1,000円程度。
外出付き添い介助料: 30分あたり1,000円~2,000円程度。
看護師の付き添い: 基本料金(2時間)12,000円などのサービスもあります。
車いすやストレッチャーなどの介護機器を使用した際に発生する料金です。
介助用車いす: 無料~1,000円程度。
ストレッチャー: 1,000円~6,000円程度。
酸素ボンベ: 1,000円~2,000円程度。
待機料金: 病院での診察待ちなどで車両が待機している時間にも料金が発生する場合があります。ただし、高速道路走行中は距離制運賃のみ適用され、待機料金は発生しません。
予約料・迎車料: 事業者によって予約料400円、迎車料900円などが別途必要になる場合があります。
深夜・早朝割増: 深夜や早朝の利用、遠距離移動、高速道路の利用など、状況に応じて追加料金が発生することがあります。
介護タクシーの料金体系は事業者によって異なるため、利用前に複数の事業者に問い合わせて、サービス内容や料金を比較検討することをおすすめします。
介護タクシーの利用において、活用できる割引や助成制度はいくつかあります。これらをうまく利用することで、経済的な負担を軽減できます。
割引制度
身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳を提示することで、タクシー運賃が10%割引になる場合があります。ただし、割引が適用されるかどうかは事業者によって異なるため、事前に確認が必要です。
助成制度
多くの地方自治体では、障害のある方や高齢者の方の社会参加を促進するため、介護タクシーの利用料金の一部を助成する制度を設けています。
福祉タクシー券: タクシー利用時に現金の代わりに使えるチケットを交付する制度です。自治体によって対象者や利用条件、助成額が異なります。
運賃助成: タクシー運賃の一部を助成する制度で、直接タクシー会社に申請する場合や、後日精算する場合があります。
これらの制度は、お住まいの市区町村によって内容が異なり、対象となる手帳の種類(例:精神障害者手帳3級が対象になる自治体もある)や所得の状況によって利用できるかどうかが決まります。詳細については、お住まいの自治体の福祉窓口やウェブサイトで確認することをおすすめします。
助成金と補助金の違い
「助成金」と「補助金」は、どちらも国や地方公共団体から支給される返済不要のお金ですが、いくつか違いがあります。
管轄: 主に厚生労働省が管轄しており、雇用や労働環境改善を目的としたものが多いです。
支給要件: 要件を満たせば、原則として受給できる可能性が高いです。
財源: 主に雇用保険料を財源としています。
管轄: 主に経済産業省や中小企業庁が管轄しており、新規事業や研究開発、設備投資などを目的としたものが多いです。
支給要件: 採択件数や金額が決められていることが多く、申請しても必ずしも受給できるとは限りません。審査があるため、提出書類の内容が重要になります。
財源: 国の予算(税金)を財源としています。
介護タクシーに関連する助成制度は、主に地方自治体が独自に実施しているものが中心です。