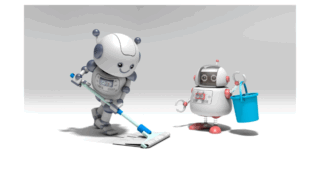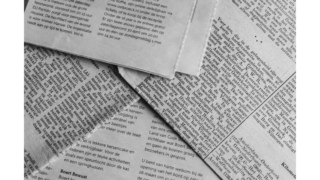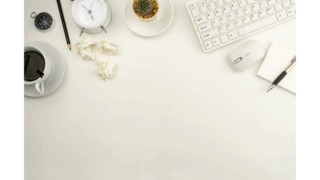介護にかかる費用の総額は、平均すると約500万円から540万円程度とされています。ただし、この金額は介護期間や介護の場所(在宅介護か施設介護か)、利用するサービスなど、様々な状況によって大きく変動します。
介護費用の内訳と平均額
介護費用は、介護の状況によって初期費用と月々の費用に分けられます。
初期費用
介護初期にかかる一時的な費用の平均は、47万円から74万円程度です。これには、以下のような費用が含まれます。
介護用ベッドや車いすなどの介護用品の購入費。
自宅をバリアフリーにするためのリフォーム費用。
月々の介護費用
月々の介護費用の平均は9万円とされていますが、15万円以上かかるケースも約2割存在します。この月々の費用は、在宅介護か施設介護かによって大きく異なります。
在宅介護の場合: 平均月額は約5万2,000円です。
施設介護の場合: 平均月額は約13万8,000円です。施設の種類によっては、入居一時金が多額になることもあります。
介護期間
介護期間の平均は4年7ヶ月から5年1ヶ月程度です。
介護保険制度による負担軽減
介護保険サービスを利用した場合、自己負担割合は所得に応じて1割から3割となります。しかし、要介護度によって利用できるサービスの上限額が決まっており、それを超えた分は全額自己負担となるため注意が必要です。
費用の準備と施設選び
将来の介護費用に備えるためには、早めの準備が大切です。公的施設は費用を抑えられる傾向にありますが、民間施設では多額の入居一時金が必要な場合もあります。どのような介護が必要か、どれくらいの費用がかかるのかを事前に情報収集し、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することも有効です。
介護費用の実態
公的年金の加入者が老後の生活保障として受け取る「老齢年金」は、原則として65歳から生涯にわたって支給され、経済的なリスクに備えるための大切な収入源となります。
年金の平均受給額
年金の受給額は加入している年金の種類や在職中の収入で変わりますが、平均的な金額は以下の通りです。
国民年金のみ:月額約6万円。
厚生年金(国民年金を含む):月額約14.4万円~21万円程度。
年金だけで介護費用は足りるのか
上記の平均額を比較すると、国民年金だけでは在宅介護や施設介護の月額費用をまかなうのは難しいことが分かります。厚生年金を受給していても、施設介護の費用によっては年金だけでは不足する可能性があります。
介護費用の負担を軽減する制度
介護費用の負担を軽減するためには、様々な公的制度を活用することが重要です。
公的介護保険:40歳以上の国民が保険料を支払い、介護が必要になった際にサービスを1~3割の自己負担で利用できる制度です。サービスの支給限度額は要介護度によって決められています。
高額介護サービス費:1ヶ月の自己負担額が上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。所得に応じて上限額が設定されており、所得が低いほど上限額も低くなります。
高額医療・高額介護合算療養費制度:医療保険と介護保険の自己負担額を年間で合算し、一定額を超えた場合に超過分が支給される制度です。
介護にかかるおむつ代や日用品の総額は、介護の状況によって変動しますが、特におむつ代は長期になると大きな金額になります。
おむつ代の目安
介護用おむつにかかる月額費用は、平均で6,000円から9,000円程度、要介護度が高い場合は7,200円から10,500円ほどになることがあります。
1日あたりの費用:おむつ1枚あたり60円〜70円、1日4〜5回の交換で240円〜350円が目安です。
月額の費用:1ヶ月では7,200円〜10,500円になります。
長期的な費用:介護期間が平均54.5ヶ月(約4年半)とすると、総額で32万7,000円〜49万500円ものおむつ代がかかる可能性があります。
施設の種類による違い
介護施設では、おむつ代が施設利用料に含まれる場合と自己負担になる場合があります。
公的介護施設:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設ではおむつ代が利用料に含まれるため、自己負担は発生しません。
民間老人ホーム:おむつ代は自己負担となることが多く、施設が用意したおむつを使うか、入居者自身がおむつを用意することになります。最近では、おむつの廃棄料がかかるところもあります。
日用品と医療費控除について
おむつは消耗品であるため、介護保険の直接的な現金給付の対象外となるのが原則です。しかし、おむつ代の負担を軽減するための制度がいくつかあります。
医療費控除:医師が発行した「おむつ使用証明書」があれば、おむつ代は医療費控除の対象になります。これは6ヶ月以上寝たきりで常におむつを使用している方が対象です。
自治体の助成制度:多くの市区町村で、独自の助成制度が設けられています。こちらも医師の意見書が必要になる場合があります。
現物支給:紙おむつの現物支給や購入補助券の配布などがあります。
購入費の助成:購入したおむつのレシートを添えて申請すると、費用の一部が助成される場合があります。
これらの制度は、要介護認定や所得などの条件があるため、お住まいの自治体に確認することをおすすめします。
日用品について
おむつ以外の介護用品には、介護保険が適用されるものもあります。
介護保険適用となる福祉用具:車椅子や介護用ベッド、手すり、スロープなど、日常生活や機能訓練をサポートする福祉用具は、介護保険を使ってレンタルや購入が可能です。
消耗品:おむつや介護用歯ブラシなどの消耗品は、原則として介護保険の対象外です。
世帯分離
世帯分離とは、同じ住所に住みながらも住民票上の世帯を分けることです。主に、介護が必要な親と同居している方が、世帯の経済的負担を軽減するために検討することが多いでしょう。世帯分離には以下のようなメリットが挙げられます。
世帯分離の主なメリット
介護費用の軽減
世帯分離をすることで、親世帯の所得が単独になります。これにより、介護サービス利用時の自己負担額や、高額介護サービス費の自己負担上限額が下がる可能性があります。特に、所得の高い子ども世代と同一世帯でいるよりも、親だけの所得で計算されることで、介護費用が軽減されやすくなります。施設入所時の居住費や食費も安くなることがあります。
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の軽減
世帯分離によって世帯全体の所得が下がると、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が安くなる可能性があります。住民税非課税世帯になることで、保険料の減額措置が適用されることがあります。
住民税の軽減
世帯分離により、所得の少ない親世代の世帯が「住民税非課税世帯」となることで、住民税が軽減されることがあります。これにより、様々な行政サービスや給付金の対象となる可能性も高まります。
家計管理の明確化
世帯分離によって家計の費用負担が分離されるため、それぞれの世帯で家計管理がしやすくなるというメリットもあります。
世帯分離は多くのメリットがある一方、国民健康保険料が逆に高くなるケースや、扶養手当・家族手当が受け取れなくなる、行政手続きが煩雑になるなどのデメリットも存在します。そのため、世帯分離を検討する際には、ご自身の世帯状況に合わせて、必ず事前にシミュレーションを行い、専門家に相談することをおすすめします。
医療費
介護にかかる医療費の総額は一概には言えませんが、高齢者の医療費は年間平均で約7.4万円とされています(2021年のデータ)。
医療費の自己負担割合
医療機関や薬局での自己負担割合は年齢によって異なります。
75歳以上:原則1割(現役並み所得者は3割)。
70歳から74歳まで:原則2割(現役並み所得者は3割)。
70歳未満:原則3割(義務教育就学前は2割)。
介護と医療の両方の費用が高額になった場合、自己負担を軽減するための制度があります。
医療費の窓口負担が、月ごとに定められた上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。上限額は、年齢や世帯収入によって異なります。
介護保険サービスの自己負担額が、所得区分に応じて設定された月額の上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。ただし、リフォーム費や施設の居住費・食費などは含まれません。
同一世帯内で年間(1年間)に支払った医療費と介護保険サービスの自己負担額を合算し、その合計額が定められた上限額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。例えば、75歳で年収200万円の方が年間の医療費30万円と介護費50万円を自己負担した場合、合計80万円のうち24万円が払い戻されることがあります。この制度の限度額も所得や年齢によって異なります。
費用負担を軽減する制度
所得が低い方が介護施設に入居する際の食費や居住費の負担を軽減する制度です。施設サービスにおける食費や居住費は原則自己負担ですが、所得の低い方には自己負担限度額を超えた分が介護保険から給付されます。この制度を利用するには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
社会福祉法人が運営する施設や事業所で、低所得により生計が困難な方が介護サービスを利用する際に、利用者負担額(介護費、食費、居住費など)の一部を軽減する制度です。原則として、利用料の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)が軽減されます。対象となるには、住民税が非課税であること、年間収入や預貯金等の額が一定基準以下であることなどの要件があります。この制度は、全ての社会福祉法人等が実施しているわけではなく、制度に協力する事業所で利用できます。
市区町村によっては、上記に加えて独自の助成制度を設けている場合があります。例えば、東京都足立区では、「生計困難者に対する利用者負担額軽減制度」を利用する方に対して、さらに区独自の制度として介護費の最大45%を助成しています。
特定の医薬品を購入した場合に、所得税の控除が受けられる制度です。
災害、失業、事業の不振など特別な理由により一時的に収入が減少し、医療費の支払いが困難になった場合に、申請により医療費の支払いが軽減されることがあります。

いずれにせよ、お金はあった方がいいことは確かです。
お金があることで、いざという時の不安が軽減され、心にゆとりが生まれます。
多くの悩みや不安は、お金と紐付いていることが多く、経済的な余裕があることで、問題が解消されやすくなります。