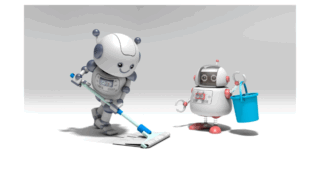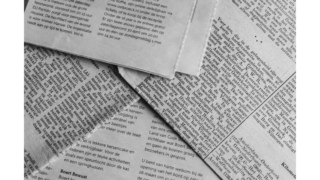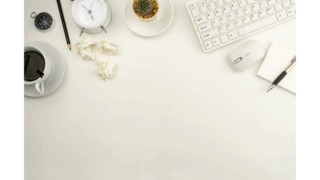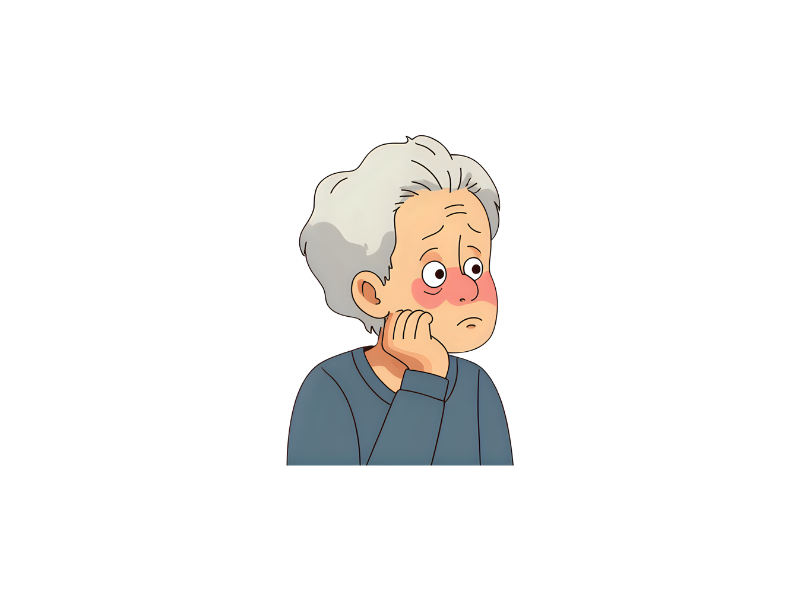
2025年65歳以上の認知症高齢者は約471.6万人(高齢者の5人に1人)12.9%と推計されています。
2040年には、約584.2万人(14.9%)に達すると見込まれています。
認知症に気付くタイミングは、多くの場合、ご自身やご家族が「あれ?いつもと違うな」と感じるようなサインが訪れます。
例えば、
・同じことを何度も尋ねる、話す。
・些細なことで怒り出す、感情的になる。
・以前は興味を持っていた活動や趣味をしなくなる。
・身なりを気にしなくなる。
・道に迷う、約束を忘れる。
・お金の管理ができなくなる、探し物が多くなる。 など
認知症とはどういうものか?
脳は、私たちのほとんどあらゆる活動をコントロールしている司令塔です。それがうまく働かなければ、精神活動も身体活動もスムーズに運ばなくなります。
認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったためにさまざまな障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態(およそ6ヵ月以上継続)を指します。
認知症の初期症状
認知症の初期症状とは?
認知症の初期症状は多岐にわたりますが、一般的には「物忘れ」が最も目立つ特徴として挙げられます。加齢による物忘れと異なり、認知症では「忘れていること自体を思い出せない」という特徴があります。
主な初期症状
物忘れ:体験したことすべてを忘れてしまうのが特徴です。例えば、朝食を食べたこと自体を忘れる、同じ話を何度も繰り返す、物の置き場所を忘れるなどが挙げられます。ゴミ出しの日を忘れたり、同じものを何度も買ってきたりすることもあります。
理解力・判断力の低下:今、何をするべきか判断が難しくなったり、新しい情報や状況を理解する能力が低下したりします。以前は簡単にできていた貯蓄の出し入れや家賃・公共料金の支払いが難しくなることもあります。
集中力・注意力の低下:集中力が続かなくなり、一つのことに長く取り組むのが難しくなる場合があります。
趣味嗜好・性格の変化:以前は温厚だった人が怒りっぽくなったり、趣味への意欲を失ったりすることがあります。身だしなみに無関心になるケースも見られます。
加齢による物忘れとの違い
加齢による物忘れは、体験の一部を忘れるだけで、忘れていることを自覚していることが多いですが、認知症による物忘れは、体験したこと自体を忘れ、その自覚がないことが特徴です。例えば、加齢による物忘れでは「朝食のメニューは思い出せないが、食べたことは覚えている」のに対し、認知症では「朝食を食べたこと自体を忘れる」といった違いがあります。
早期発見の重要性
認知症は早期に発見し、適切な治療を開始することで、症状の進行を遅らせることができる場合があります。もし、本人や周囲の人に上記のような症状が見られる場合は、早めに医療機関に相談することが大切です。
認知症受診の重要性
1. 早期治療で症状の進行を遅らせる効果
薬物療法の効果向上: 認知症の初期段階であれば、進行を遅らせる薬やケアが効果を発揮しやすいです。進行が進むと、薬の効果が見られにくくなるケースもあります。アルツハイマー型認知症の場合は、早い時期から薬の服用を開始することで、症状の軽い状態をより長く維持できる可能性があります。
生活の質の維持・改善: 早い段階で適切な支援を受けることで、認知機能の低下を遅らせ、ご本人の生活の質を保つことにつながります。
2. 治る可能性がある別の病気の発見
鑑別診断(病気を見分ける)の必要性: 認知症と似た症状を引き起こす病気の中には、治療によって症状が改善したり、完治に近い状態まで回復するものもあります。例えば、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、甲状腺機能低下症、ビタミン欠乏症、うつ病などが挙げられます。
早期治療で回復: これらの病気は、適切な時期に治療を受ければ治りますが、治療が遅れると効果が期待できないことがあります。そのため、まずは認知症かどうか、他の病気の可能性があるかどうかを正確に診断することが非常に重要です。
3. 将来の生活設計と介護計画にゆとりが持てる
介護計画の準備: 早期に診断を受けることで、今後の生活や介護に関する計画を立てる十分な時間を確保できます。認知症が進行してからでは、施設探しの選択肢が限られてしまう可能性もあります。
ご本人の希望の反映: 症状が軽いうちに、ご本人とご家族が病気について話し合い、今後の生活や介護に関する希望を共有することができます。これにより、症状が進行した場合でも、ご本人の意思が尊重されたケアを受けやすくなります。
経済的な計画: 認知症の介護には費用がかかることが多いため、早期診断によって、介護保険サービスの利用や住宅改修など金銭的な計画を立てる時間を持つことができます。成年後見制度の利用や財産管理の方法などについても、早めに準備を進められます。
4. 介護者の負担軽減
適切なケアプラン: 早期に診断を受けることで、ご本人に合った適切なケアプランを立てたり、利用できる介護サービスを探したりすることができます。これにより、介護者の負担を軽減し、ご家族が孤立せずに介護を続けやすくなります。
周囲の理解: 認知症と診断されることで、周囲の人がご本人の症状に合わせた対応について学ぶことができ、ご本人の変化に対する理解が得られやすくなります。
5. 相談先の確保
専門機関の活用: 早期に専門機関(かかりつけ医、もの忘れ外来、認知症疾患医療センター、地域包括支援センターなど)に相談することで、適切なサポートを受けられます。
継続的な認知機能測定: たとえ認知症と診断されなかった場合でも、定期的に認知機能の測定を行うことで、早期の変化に気づき、より早く対処できる可能性が高まります。
どのように受診すれば良いか
まずはかかりつけ医へ: 日頃から体の状態を把握しているかかりつけ医に相談するのがおすすめです。必要に応じて専門医への紹介状を書いてもらうことができます。
もの忘れ外来: 認知症専門の「もの忘れ外来」や「認知症専門外来」を直接受診するのも良いでしょう。
地域包括支援センター: どこに相談すればよいか迷う場合は、地域包括支援センターに相談すると、適切な医療機関やサービスを紹介してもらえます。
ご本人が受診をためらう場合は、「健康診断」として通院を促したり、他の人のエピソードを話して自覚を促すなどの工夫も有効です。強制するのではなく、本人の気持ちを理解した上で、自尊心を傷つけないように受診を勧めることが大切です。
現在よく使われている主な認知症治療薬
現在、日本で主に使われている認知症治療薬は以下の4種類です。これらは主にアルツハイマー型認知症の治療に使われますが、一部はレビー小体型認知症にも適用されます。
アリセプト®(ドネペジル)
作用: 脳内の神経伝達物質「アセチルコリン」の分解を抑え、神経細胞の働きを活性化させます。
対象: アルツハイマー型認知症の初期から高度まで幅広いステージの進行を遅らせ、記憶障害を緩和する効果が期待できます。レビー小体型認知症にも適用されます。
剤形: 錠剤、口腔内崩壊錠、ゼリー、貼り薬などがあります。
副作用: 吐き気、嘔吐、食欲不振、下痢などの消化器症状が比較的多く見られます。興奮や不整脈などの報告もあります。
作用: アセチルコリンの分解を抑え、さらにアセチルコリンを受け取る受容体の感受性を高めて神経伝達を助けます。
対象: アルツハイマー型認知症の軽度から中等度の進行を遅らせ、記憶障害や見当識障害の症状を抑制する効果が期待できます。
剤形: 錠剤、口腔内崩壊錠、内用液があります。
副作用: 吐き気、嘔吐、食欲不振、下痢などの消化器症状が見られることがあります。
作用: アセチルコリンの分解を抑制し、認知機能の低下を緩やかにします。
対象: 軽度から中程度のアルツハイマー型認知症に適用されます。
剤形: 飲み薬が苦手な方でも使用できる貼り薬です。皮膚から成分が持続的に吸収されるため、血中濃度を一定に保ちやすいという利点があります。
副作用: 貼り薬のため、かぶれやかゆみなどの皮膚症状が出ることがあります。消化器症状が出る場合もあります.
作用: 脳内の神経伝達物質「グルタミン酸」の過剰な働きを抑え、神経細胞を守ることで、認知機能の低下を抑制します。他の3種類の薬とは作用メカニズムが異なるため、併用されることもあります。
対象: アルツハイマー型認知症の中等度から高度の症状に適用され、興奮や攻撃性といった行動・心理症状(BPSD)の緩和にも効果が期待されます。
剤形: 錠剤、口腔内崩壊錠などがあります。
副作用: めまい、頭痛、眠気、便秘などが見られることがあります。消化器症状は他の3種類の薬に比べて少ない傾向があります。
🆕 最新の認知症治療薬
近年、アルツハイマー病の原因とされる脳内の異常なたんぱく質(アミロイドβ)に直接作用する新しいタイプの薬が開発され、注目を集めています。これらの薬は「疾患修飾薬」と呼ばれ、病気の根本原因に働きかけることが期待されています。
特徴: 脳内に蓄積したアミロイドβ(異常なたんぱく質)を取り除くことで、アルツハイマー病の進行を遅らせることを目指す薬です。
対象: アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)または軽度の認知症の患者さんが対象となります。
投与方法: 2週間に1回、点滴で投与されます。
効果: 2023年9月に厚生労働省に承認され、病気の進行を遅らせ、認知機能の低下を緩やかにすることが示されています。臨床試験では、プラセボと比較して症状の進行を約27%抑制したと報告されています。
副作用: 脳に浮腫(ARIA-E)や出血(ARIA-H)が起こる「アミロイド関連画像異常(ARIA)」が主な副作用として挙げられます。点滴中に発熱、悪寒、発疹、吐き気などの症状が出ることもあります。定期的なMRI検査による経過観察が必要です。
特徴: レカネマブと同様に、アミロイドβタンパク質に作用し、脳に沈着したアミロイド斑をターゲットとします。
対象: レカネマブと同じく、アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)または軽度の認知症の患者さんが対象です。
効果: 国際共同治験では、治療開始後17.5か月で5.44か月の進行抑制効果が認められたと報告されています。2024年秋に厚生労働省により製造販売が承認されました。
副作用: レカネマブと同様にARIA(アミロイド関連画像異常)が報告されています。
服用上の注意と副作用について
完治はしない: これらの薬は認知症を完治させるものではなく、あくまで症状の進行を遅らせたり、緩和したりするのが目的です。
早期発見が重要: 軽度のうちから薬を服用することで、症状の軽い状態を長く保てる可能性があります。
副作用: どの薬にも副作用はあります。特に消化器症状(吐き気、嘔吐、食欲不振、下痢)や、めまい、眠気などが挙げられます。新薬であるレカネマブやドナネマブでは、脳浮腫や脳出血を起こす可能性(ARIA)があるため、定期的な検査が必要です。
自己判断での中止は危険: 副作用がつらいと感じても、自己判断で服用を中止するのは危険です。症状が急激に悪化したり、他の病気のサインを見逃したりする可能性があります。必ず医師に相談してください。
多剤服用(ポリファーマシー)に注意: 高齢者は複数の病気を抱え、多くの薬を飲んでいる場合があります。薬の数が増えると、相互作用による予期せぬ副作用や、肝臓・腎臓への負担が増すことがあります。認知症の薬だけでなく、服用している全ての薬を見直すことで、症状が改善するケースもあります。
非薬物療法との併用: 薬物療法だけでなく、リハビリテーションやレクリエーション、生活環境の調整といった非薬物療法も大切です。これらを組み合わせることで、より良い効果が期待できます.
本日(2025年9月)時点での情報です。新しい治療薬の開発や承認は常に進んでいますので、最新の情報は主治医や薬剤師にご確認いただくことをおすすめします。
認知症になること、認知症になった人を受け入れることには、時間が必要です。
少しづつ理解して、少しづつ受け入れていき、心を整えていく時間です。
そしてだんだん、受け止めていけるようになっていきます。
認知症になることは、恥ずかしいことでも隠すことでもなく、あたりまえに労わりあえる社会になることを願います。