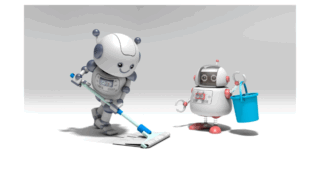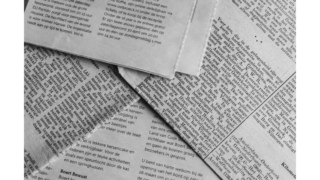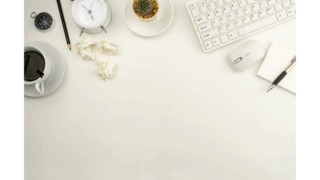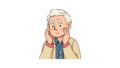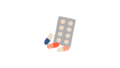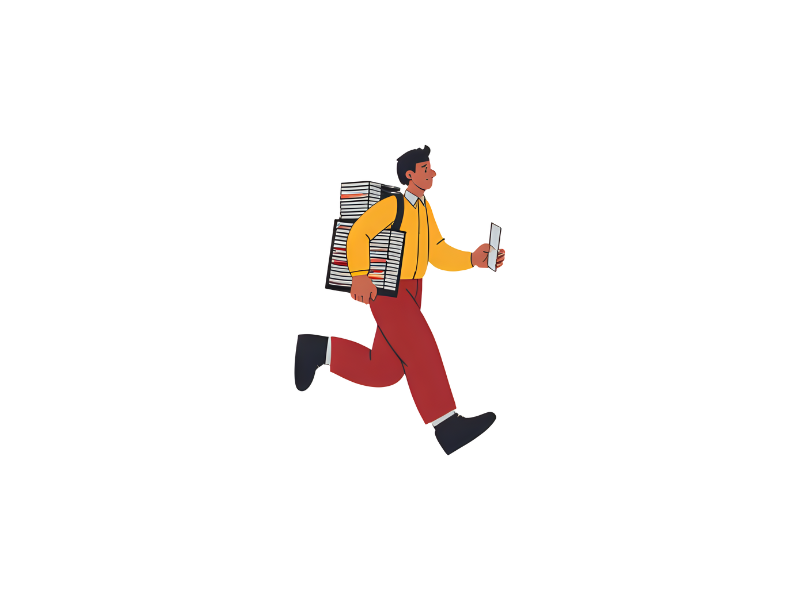
介護保険制度が「分かりにくい」と感じられる背景には、主に以下の要因が挙げられます。
財源と費用負担の複雑さ
介護保険制度の財源は、公費(税金)と40歳以上の国民が支払う介護保険料で成り立っています。
介護報酬(介護給付費)の50%は公費で賄われています。この公費は国、都道府県、市区町村がそれぞれ負担しています。
残り50%は40歳以上の国民が支払う保険料で、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳〜64歳)が負担します。この保険料の割合は、時期によって見直されています。
サービス利用時の自己負担は原則1割ですが、所得に応じて2割または3割になることがあります。施設サービスでは、これに加えて居住費や食費なども自己負担となります。
このように、財源が複数の要素から成り立ち、自己負担割合も所得によって変動するため、複雑に感じられることがあります。
対象者と利用条件の多様性
介護保険サービスの対象者は年齢や状態によって異なります。
第1号被保険者(65歳以上): 要介護または要支援と認定されれば、原因を問わずサービスを利用できます。
第2号被保険者(40歳〜64歳): 医療保険に加入しており、特定の16種類の疾病(特定疾病)が原因で要介護または要支援と認定された場合にのみ、サービスを利用できます。特定疾病には、がん(末期)、関節リウマチ、初老期の認知症などが含まれます。
40歳から保険料が発生するにもかかわらず、65歳未満の場合は原因疾患が限定される点が分かりにくさを生む一因です。
申請からサービス利用までの多段階性
介護保険サービスを利用するためには、まず要介護認定を受ける必要があり、そのプロセスが多段階で複雑です。
申請: 市区町村の窓口や地域包括支援センターで申請を行います。
認定調査: 調査員が利用者の自宅などを訪問し、心身の状態に関する74項目以上の詳細な調査を行います。
主治医意見書: 主治医が医学的見地から意見書を作成します。
一次判定: 調査結果と主治医意見書の一部をコンピュータに入力し、全国一律の方法で一次判定を行います。
二次判定: 介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家で構成)が、一次判定の結果や主治医意見書などをもとに総合的に審査し、要介護度を決定します。
結果通知: 申請から原則30日以内に、認定結果が通知されます。
この複雑な手続きの流れは、利用者にとって大きな負担となり、分かりにくいと感じる原因となります。

いくつも工程がありすぎ!
道のりが長いと、届いたころには忘れている方も!
要介護認定の有効期間と更新制度
要介護認定には有効期間が定められており、継続してサービスを利用するためには更新が必要です。
有効期間: 新規申請の場合、原則6か月(状態に応じて3~12か月)。更新申請の場合、原則12か月(状態に応じて3~48か月)です。
自動更新ではない: 要介護認定は自動で更新されないため、有効期間満了日までに更新申請を行わなければ、サービスが利用できなくなります。
区分変更: 認定期間中に心身の状態が大きく変化した場合は、有効期間を待たずに「区分変更申請」を行うことができます。
これらの「有効期間」や「更新」といった制度が、医療保険とは異なるため、利用者に混乱を生じさせることがあります。

自動更新ではないため、しっかりと時期を覚えておかなければなりませんね。
有効期間が切れてもお知らせが来るわけじゃないので、ほとんどはケアマネさんが管理しているようです。