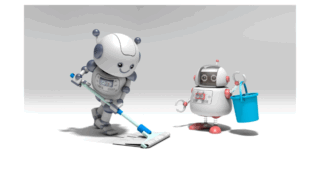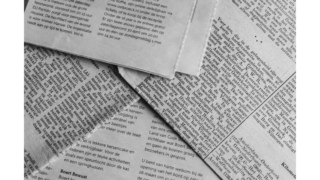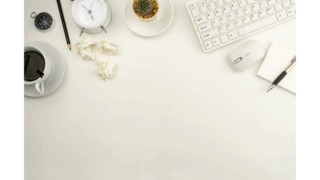ビジネスケアラー
ビジネスケアラーとは、仕事をしながら家族の介護を行っている人のことを指します。
職場の理解を得る
実はこれが一番難しい・・。介護と仕事を両立するために、まずは職場に現状を伝え、理解してもらうことが大切です。
介護をしていることをオープンにすることで、上司や同僚からの協力や、業務調整の理解を得やすくなります。
理由を伝えずに遅刻や早退を繰り返すと、周囲の理解を得にくくなる可能性があります。
外部サービスや制度を活用する
一人で抱え込まず、外部のサービスや国の支援制度を積極的に活用しましょう。
役所や地域包括支援センター: 介護事業者や介護サービスについて相談できます。
ケアマネジャー: 介護プランの作成だけでなく、介護者の精神的・身体的負担の悩みについても具体的な対策を相談できます。要介護認定の申請後、担当のケアマネジャーがついてくれます。
介護保険サービス: 介護保険サービスを上手に利用することで、介護の負担を減らすことができます。
育児・介護休業法に基づく制度: 介護休業、介護休暇、短時間勤務などの制度は、仕事と介護の両立に役立ちます。2025年4月には法改正も施行され、より利用しやすくなりました。
家族や周囲との協力
家族や周囲の人々と良好な関係を築き、協力を得ることも重要です。
家族と介護について話し合い、役割分担をすることで、一人に負担が集中するのを防げます。
近所の人々との関係もいざという時に助けになることがあります。
自分の時間も大切にする
介護と仕事の両立は精神的・身体的に大きな負担となるため、自分の時間を確保してリフレッシュすることが必要です。
社会とのつながりを保つことは、孤独感を軽減し、ストレスを緩和する上で重要です。
介護離職を防ぐための具体的な支援制度について詳しく説明します。
介護離職は、働き盛りの世代に多く、企業にとっても個人にとっても大きな損失となる社会問題です。この問題を防ぐために、国や自治体、そして企業がさまざまな支援策を講じています。
企業が取り組む支援
企業は、従業員が仕事と介護を両立できるよう、柔軟な働き方をサポートし、相談しやすい環境を整えることが求められています。
柔軟な働き方の提供:テレワーク、時短勤務、時差出勤、中抜け勤務など、従業員の介護状況に合わせて柔軟な働き方を選べるようにすることで、離職を防ぎやすくなります。急な介護にも対応できるよう、勤務時間や曜日が固定されていない働き方が理想的です。
社内制度の整備・周知:介護休業や介護休暇、短時間勤務制度などを就業規則に明記し、従業員が制度を認知して利用できるよう、周知を徹底することが重要です。特に2025年4月からは、改正育児・介護休業法により、企業には個別の周知・意向確認、40歳時点での情報提供、相談窓口の設置などが義務付けられています。
相談体制の強化と情報提供:社内に相談窓口を設置したり、外部の専門家と連携したりして、従業員が安心して介護について相談できる体制を整えることが大切です。介護サービスの種類や利用方法、施設の選び方などの情報提供も有効です。
管理職への研修:介護に関する知識を深め、部下の介護状況を理解し、適切にサポートできるよう、管理職向けの研修を実施することが推奨されています。
従業員の実態把握:アンケートや面談などを通じて、従業員の介護状況やニーズを把握し、自社に必要な支援策を検討します。特に40代から50代は介護に直面する可能性が高いため、プライバシーに配慮しつつ、業務への影響を把握することが重要です。
国や自治体の支援制度
国も介護離職防止を重要な課題と位置づけ、さまざまな支援制度を設けています。
育児・介護休業法に基づく制度
介護休業:対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分けて取得できる制度です。休業中には、一定の要件を満たせば「介護休業給付金」が支給され、休業前賃金の約67%相当額が受け取れます。
介護休暇:対象家族1人につき年度で5日まで(2人以上の場合は10日まで)取得でき、1日単位または時間単位で利用可能です。2025年4月からは、勤続6ヶ月未満の労働者も取得できるよう制度が改正されました。これまで「継続雇用期間が6ヶ月未満の労働者を除外」といった規定がありましたが、これが廃止されることで、入社間もない従業員でも介護休暇を取得できるようになりました。
短時間勤務、所定外労働の制限(残業免除)、時間外労働・深夜業の制限:介護をしながら働き続けられるよう、労働時間を短縮したり、残業や深夜勤務を免除したりする制度です。
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース):中小企業が、従業員の円滑な介護休業の取得や職場復帰、介護と仕事の両立支援に取り組む場合に支給される助成金です。
「介護支援プラン」の作成、介護休業取得時、職場復帰時、柔軟な働き方支援などの取り組みに対して助成金が支給されます。
2025年度からは、中小企業が介護休業中の従業員の業務を代替する同僚への手当や、新規雇用に対しての補助金が増額される予定です。
これらの支援策を組み合わせることで、介護離職を未然に防ぎ、従業員が安心して働き続けられる環境を整えることができます。
ダブルケアラー
ダブルケアラーとは、育児と介護を同時に行っている人のことを指します。
育児休業と介護休業はどちらも取得できますが、同時に両方の休業給付金を受け取ることはできません。ただし、制度の利用にはいくつかの工夫や考慮すべき点があります。
育児休業について
育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できます。保育所に入れないなどの事情がある場合は、1歳6ヶ月、さらに2歳まで延長が可能です。男性も育児休業を取得でき、最近では男性の取得率も増加傾向にあります。
介護休業について
介護休業は、要介護状態にある家族1人につき、通算93日まで、3回を上限に分割して取得できます。介護休暇は、要介護状態にある家族1人につき年間5日まで、2人以上の場合は年間10日まで取得可能です。介護休暇は1日単位または時間単位で取得できます。
ダブルケアにおける休業給付金
育児休業中に介護休業が必要になった場合やその逆の場合でも、同時に育児休業給付金と介護休業給付金の両方を支給されることはありません。そのため、育児と介護が同時に発生する「ダブルケア」の場合、現状の制度下では、どちらか一方の給付金を選択するか、休業期間をずらすなどの工夫が必要となります。
知っておきたいポイント
社会保険料の免除: 育児休業中や産前産後休業中は、社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除される場合があります。
不利益取扱いの禁止: 育児休業や介護休業の取得を理由に、会社が不利益な扱いをすることは法律で禁じられています。
職場環境の整備: 厚生労働省は、仕事と育児、仕事と介護の両立を支援するため、企業に対して職場環境の整備を促しています。
ヤングケアラー
ヤングケアラーとは、「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子供や若者」のことを指します。具体的には、障害や病気のある家族の代わりに、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしたり、幼いきょうだいの世話をしたりする子供たちが該当します。
日本における定義と現状
「子ども・若者育成支援推進法」では、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、国や地方公共団体が支援に努めるべき対象としてヤングケアラーを明記しています。
2021年度(令和3年度)の調査では、小学6年生の約15人に1人が家族の世話をしていると回答しており、健康状態や学校生活に影響が出ていることが懸念されています。家族の手伝いは大切なことですが、それが子どもの学業や友人関係、心身の健康に悪い影響を与えるほどの重い負荷になっている場合は注意が必要です。
ヤングケアラーが直面する問題
ヤングケアラーが直面する問題は多岐にわたります。
心身への影響: 精神的なストレスや身体的な疲労を感じやすく、心や体に不調をきたすことがあります。
学業への影響: 宿題をする時間がなかったり、遅刻や早退が増えたりと、学校生活に支障が出ることがあります。
社会生活への影響: 友人との遊びや自分のための時間が取れず、孤立してしまうことがあります。
支援の必要性
ヤングケアラーの子どもたちは、「家族を助けるのは当たり前」と感じて、自分がヤングケアラーであることに気づいていないこともあります。大切なのは、ケアすること自体を否定せず、その子が子どもらしくいられる選択肢を広げ、多角的なサポートを提供することです。政府も「ヤングケアラー認知度向上の集中取組期間」を設け、社会全体での認知度向上と支援体制の強化に取り組んでいます。