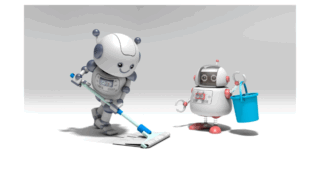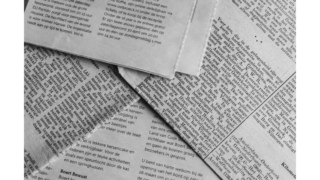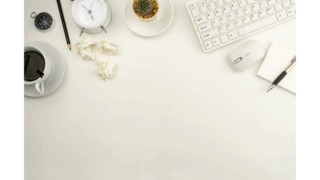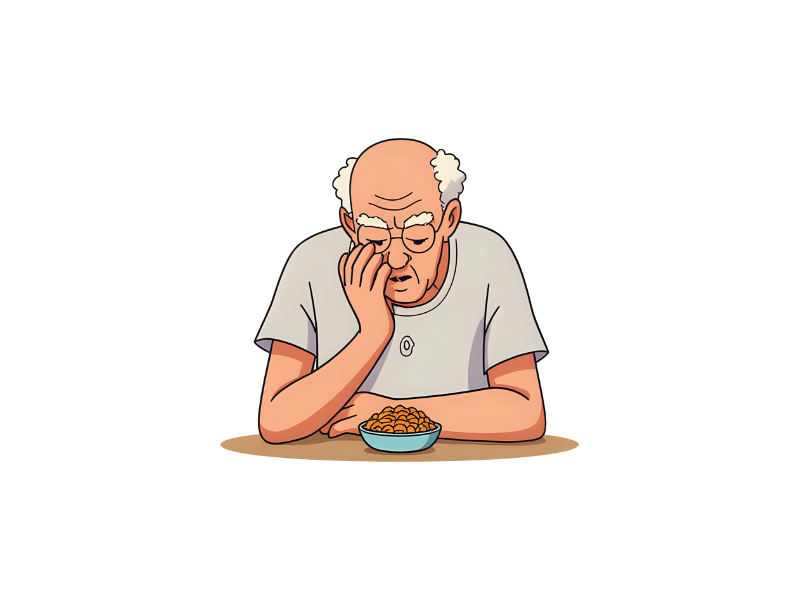
誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)は、食べ物や唾液、胃液などが誤って気管に入り、それが原因で肺に炎症が起きる病気です。一般的に、飲み込む機能(嚥下機能)の低下によって引き起こされます。
誤嚥性肺炎のメカニズム
通常、食べ物などが気管に入りそうになると、咳をして排出する反射機能が働きますが、この機能が衰えると、食べ物などが肺に入り込んで肺炎になることがあります。
加齢や病気によって嚥下機能が低下すると、食べ物や唾液が誤って気管に入りやすくなります。特に高齢者では、健康な方でも嚥下機能が低下し、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。
口腔内に存在する細菌が唾液や食べ物と一緒に気管に入り込むことで、肺炎を引き起こします。高齢者や寝たきりの方では、口腔ケアが不十分なこともあり、肺炎の原因となる細菌が増殖しやすい傾向にあります。

高齢者の誤嚥性肺炎には、いくつか独自の特徴があります。加齢による体の変化が大きく影響しているため、若い方とは異なる側面が見られます。
誤嚥性肺炎が高齢者に多い理由
高齢になると、食事を飲み込む際に食べ物が気管に入りそうになっても、それを防ぐための反射機能が弱まる傾向にあります。また、以下のような要因も誤嚥性肺炎のリスクを高めます。
嚥下機能の低下: 加齢による筋力低下や、脳卒中、神経疾患といった病気によって、食べ物や唾液をうまく飲み込めなくなることがあります。
咳反射の低下: 気管に異物が入ったときに強く咳き込んで排出する力が弱まります。
免疫力の低下: 全身の抵抗力が落ちるため、細菌に感染しやすくなります。
口腔内の細菌増加: 唾液の分泌量が減ったり、口腔ケアが不十分になったりすることで、口の中の細菌が増えやすくなります。
特に、寝たきりの方ではこれらの機能がさらに低下し、誤嚥性肺炎を発症するリスクが高まることが知られています。
高齢者特有の症状
誤嚥性肺炎は発熱や咳、痰といった一般的な肺炎の症状を示すことが多いですが、高齢者の場合はこれらの症状が出にくい「非典型的な症状」が特徴です。
元気がない: なんとなく元気がない、ぼんやりしているなど、漠然とした体調不良が見られます。
食欲不振: 食欲が低下し、食事量が減ることがあります。
傾眠傾向: 眠っている時間が長くなることがあります。
不明顕性誤嚥: 食事中以外、例えば睡眠中に唾液が気管に入ってしまうなど、本人も気づかないうちに誤嚥を繰り返しているケースもあります。
これらの症状は風邪と間違われやすいため、高齢者の体調変化には注意が必要です。
重症化のリスク
高齢者は誤嚥性肺炎が重症化しやすい傾向にあり、日本の死因の上位を占める要因の一つともなっています。一度肺炎にかかると、長引きやすく、再発もしやすいという特徴があります。
嚥下機能が低下する原因は、大きく分けて「器質的原因」「機能的原因」「心理的原因」の3つがあります。これらの原因が複合的に絡み合って、嚥下機能の低下を引き起こすことも少なくありません。
器質的原因
これは、食べ物が通る道やすでに飲み込みに関わる器官そのものに問題がある場合を指します。
炎症や腫瘍:口内炎や咽頭炎、食道がん、喉頭がんなどの炎症や腫瘍が食べ物の通り道を塞いでしまうことがあります。咽頭炎は風邪が原因のこともありますが、長引いたり繰り返したりする場合は注意が必要です。
形態異常:先天的な唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)や、手術による食道の一部切除なども、嚥下機能に影響を及ぼすことがあります。
機能的原因
食べ物を飲み込むために必要な神経や筋肉の働きに異常がある場合です。
脳血管障害:脳梗塞や脳出血などの脳卒中は、嚥下を司る脳の機能に影響を与え、嚥下反射がうまく働かなくなることがあります。嚥下障害の原因の約45%は脳血管疾患によるものです。
神経筋変性疾患:パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、重症筋無力症などの神経の病気も、嚥下に必要な筋肉や神経に影響を与えるため、嚥下機能が低下します。
筋力低下:年齢を重ねると、全身の筋力が低下するのと同様に、飲み込みに関わる舌や喉の筋肉も弱くなります。特に、のど仏が上がりにくくなる、口腔内の知覚が鈍るといった変化は、嚥下反射の遅れにつながります。
唾液分泌量の減少:唾液が減ると、食べ物をまとめにくくなり、飲み込みにくさを感じることがあります。
歯の喪失や咀嚼能力の低下:歯が少なくなったり、噛む力が弱くなると、食べ物をしっかり噛み砕くことができず、飲み込みやすい形にまとめるのが難しくなります。
サルコペニア:近年、高齢者に多いサルコペニア(加齢に伴う筋肉量と筋力の低下)が、嚥下障害の新しい原因として注目されています。入院中の高齢者が活動量の低下や栄養不足に陥ることで、サルコペニア性嚥下障害を発症・悪化させることもあります。
薬剤の副作用:鎮静剤や向精神薬、その他一部の薬剤の副作用として、嚥下に関わる器官の機能が低下することもあります。
心理的原因
精神的な要因が嚥下機能に影響を与えることもあります。
認知症:食べ物の認識や、食事の必要性を理解する能力が低下し、食事を拒否したり、うまく食べられなくなることがあります。
うつ病:うつ病による食欲不振が、結果的に嚥下機能の低下につながることもあります。
嚥下機能の低下は、様々な原因が複雑に絡み合って起こるものです。気になる症状があれば、医療機関に相談することが大切です。
予防のポイント
口腔ケアは、単にお口の中をきれいにするだけでなく、全身の健康を守るために非常に重要です。特に高齢者にとっては、その重要性がさらに増します。
口腔ケアの基本的な目的
口腔ケアの目的は多岐にわたりますが、主に以下の点が挙げられます。
口腔内の清潔を保つ:虫歯や歯周病、口内炎といったお口のトラブルの予防です。
口腔機能の維持・向上:食べ物を噛む、飲み込む、発音するといったお口本来の機能を維持し、回復させることです。これには、嚥下(えんげ)機能のトレーニングやリハビリも含まれます。
生活の質(QOL)の向上:お口の中が清潔で快適だと、美味しく食事ができ、会話も弾み、表情も豊かになります。口臭の予防にもなり、自信を持って社会生活を送ることにもつながります。
全身の健康との深い関係
口腔ケアが特に重要視されるのは、お口の健康が全身の健康状態に大きく影響するからです。
誤嚥性肺炎の予防
細菌の侵入防止:お口の中には多くの細菌が生息しており、口腔ケアが不十分だとこれらの細菌が増殖します。特に高齢者の場合、唾液や食べ物と一緒にこれらの細菌が誤って気管に入り込む(誤嚥)と、肺で炎症を起こし誤嚥性肺炎を引き起こすリスクが高まります。口腔ケアで口内を清潔に保つことは、この細菌数を減らし、誤嚥性肺炎の予防に直結します。
嚥下機能の維持:咀嚼や嚥下(飲み込み)のリハビリを含む機能的口腔ケアは、誤嚥そのものを防ぐ効果も期待できます。
その他の全身疾患の予防・改善
お口の中の細菌は、誤嚥性肺炎だけでなく、さまざまな全身疾患に関与していると考えられています。
食欲増進と栄養状態の改善
舌の汚れを取り除いたり、唾液の分泌を促すケアを行うことで、味覚が改善され、食欲が増進します。美味しく食事が摂れることは、栄養状態の改善につながり、全身の免疫力維持にも貢献します。
介護における口腔ケアの重要性
口腔ケアは、介護を受ける方だけでなく、介護をする方にとっても大きなメリットがあります。適切な口腔ケアによって全身の健康が維持されれば、病気による入院や体調悪化が減り、介護負担の軽減にもつながります。
このように、口腔ケアは虫歯や歯周病といったお口のトラブルを防ぐだけでなく、誤嚥性肺炎をはじめとする全身の病気を予防し、生活の質を高めるために不可欠な習慣なのです。
誤嚥性肺炎と入れ歯の関係
入れ歯をしている方が誤嚥性肺炎のリスクが高まる可能性はいくつかあります。
口腔内の細菌増加:入れ歯の清掃が不十分だと、入れ歯の表面に食べカスやプラーク(歯垢)が溜まり、口の中の細菌が増殖します。この細菌が誤嚥によって肺に入ると、肺炎になるリスクが高まります。
嚥下機能の低下:高齢になると、唾液量の減少、歯の状態、筋力の低下などにより、飲み込む力が弱まります。入れ歯が合っていないと食べ物をうまく噛み砕けず、飲み込みにくくなることがあります。また、嚥下障害のある方が上下両方の入れ歯を入れると、舌の動きが制限され、さらに飲み込みにくくなる可能性もあります。
誤嚥性肺炎を防ぐための入れ歯ケア
誤嚥性肺炎を防ぐためには、口腔内と入れ歯を清潔に保つことが非常に重要です。
毎日のお手入れ:入れ歯は毎日、専用のブラシと洗浄剤を使って丁寧に清掃しましょう。天然歯も同様に、食事のたびに歯磨きをして食べカスやプラークを除去することが大切です。
定期的な歯科受診:月に一度は歯科医院で入れ歯の状態をチェックしてもらい、調整することが推奨されています。定期検診では、口腔内の清掃や嚥下機能の確認も行われます。
お口のトレーニング:嚥下機能を鍛えるための「あいうえお体操」などのトレーニングも誤嚥性肺炎の予防に役立ちます。
誤嚥性肺炎の予後
誤嚥性肺炎の予後は、特に高齢者において注意が必要です。日本の死因の上位に位置する病気であり、予防と早期対応が非常に重要となります。
高齢者における予後の厳しさ
誤嚥性肺炎は、特に高齢者にとって予後(病気の経過や結末)が厳しい疾患です。高齢者の肺炎の多くは誤嚥性肺炎が原因であり、70歳以上の肺炎の7割以上、90歳以上では95%近くが誤嚥性肺炎だと言われています。厚生労働省のデータによると、肺炎患者の約7割が75歳以上の高齢者です。
2024年の研究結果によると、誤嚥性肺炎で入院した高齢患者の退院後の生存期間中央値は約1年と短く、退院5年後の生存割合はわずか13%という報告もあります。
栄養摂取手段との関連
退院時の栄養摂取手段も予後に大きく影響します。
経口摂取(口から食事): 約1年8か月
経管栄養(鼻からチューブや胃ろうなど): 約9か月
点滴: 約1か月
このデータから、口からの食事ができなくなることは、予後をさらに悪化させる要因となることがわかります。
死亡リスクを高める要因
以下の要因は、誤嚥性肺炎による死亡リスクを高める可能性があります。
性別: 男性は女性に比べて死亡リスクが約2.4倍。
低栄養: BMI 18.5kg/m²未満の低栄養状態の人は、それ以上の人に比べて死亡リスクが約2.2倍。
栄養摂取手段: 退院時の栄養摂取手段が経管栄養の場合は経口摂取に比べて約1.7倍、点滴の場合は約4.4倍、死亡リスクが高まります。
肺炎の再燃: 入院中に肺炎が再燃すると、死亡退院につながりやすいことが示唆されています。
予後改善のために
誤嚥性肺炎の予後を改善するためには、予防策の徹底はもちろんのこと、発症してしまった場合の早期かつ適切な治療、そして再発予防のための継続的なケアが不可欠です。
嚥下機能のリハビリテーション: 嚥下機能の低下は誤嚥性肺炎の主要な原因であるため、リハビリテーションを通じて嚥下機能の維持・改善を図ることが重要です。
口腔ケア: 口腔内の清潔を保ち、細菌の増殖を抑えることが、感染症の予防に繋がります。
全身状態の管理: 栄養状態の改善や適切な運動などによる体力維持も、予後を左右する重要な要素です。
誤嚥性肺炎は一度発症すると再発しやすい病気で、特に高齢者にとっては重篤な結果を招くことがあります。再発を防ぐための取り組みが非常に重要視されています。
誤嚥性肺炎の再発率
誤嚥性肺炎は「繰り返す」病気として認識されており、再発の危険が常に伴います。具体的な再発率は、調査対象や期間によって異なりますが、いくつかの病院では以下のような報告があります。
ある病院のデータでは、4週間以内に呼吸器系疾患で再入院する誤嚥性肺炎の患者さんの割合は、年度によって変動がありますが、2019年度から2022年度にかけては3.0%から7.2%の範囲でした。2023年度には0%になったと報告されていますが、これはTQM(総合的品質管理)活動の一環として言語聴覚士、看護師、栄養部門が連携して嚥下指導マニュアルを作成し、改善に取り組んだ成果の可能性があります。
別の病院のデータでは、2016年度から2019年度にかけて、4週間以内の誤嚥性肺炎で再入院する割合は2.65%から5.56%の範囲で推移していました。
これらのデータは、短期的な再入院率を示しており、長期的な再発率についてはさらに高くなる可能性があります。
再発の危険性とその認識
誤嚥性肺炎は、一度治癒したとしても、誤嚥の原因となる嚥下機能の問題が残っている限り、常に再発のリスクを抱えています。特に、食事中にムセ込む「顕性誤嚥」だけでなく、睡眠中に唾液などが無自覚に気管に入り込む「不顕性誤嚥」が主な誤嚥性肺炎の原因であり、これも再発につながりやすい要因です。
再発を繰り返す誤嚥性肺炎は、入院期間の長期化や、ADL(日常生活動作)の低下、全身状態の悪化といった悪循環に陥る可能性が高く、退院調整が難しくなることもあります。
再発予防の重要性
医療の進歩した現代においても、誤嚥性肺炎は高い死亡率を伴う恐ろしい疾患であり、何度も繰り返すという認識を持つことが重要です。誤嚥のリスクを減らし、口腔ケアを徹底するなど、日々の予防策が再発防止に不可欠です。
経口摂取ができなくなった場合の栄養補給の方法
口から食事が摂れない、あるいは摂取量が不十分な場合、腸が機能しているかどうかで見極め、医学的適応に基づいて栄養投与法が選択されます。
腸管が利用できる場合
腸管が利用できる場合は、経腸栄養が選択されます。腸管を使う方が生理的なので、世界的なコンセンサスとなっています。
経鼻チューブ:一時的(4週間未満)な場合は、鼻から胃にチューブを留置して栄養を補給します。
胃ろう・腸ろう:長期(4週間以上)にわたる場合は、胃や腸に直接チューブを挿入し、栄養を補給します。
腸管が利用できない場合
腸管が利用できない場合は、静脈栄養が選択されます。
末梢静脈栄養:腕や足の血管から点滴で栄養を補給します。水分やミネラル、ビタミンなどが中心で、カロリーになる栄養分は少量しか含まれません。一時的な脱水症状の改善などには有効ですが、栄養の補給としては十分でないことが多いです。
中心静脈栄養:十分な栄養量を投与する必要がある場合、太い血管(中心静脈)から高濃度の栄養剤を点滴します。
家族ができることと心構え
口から食事が摂れなくなった状況では、ご本人やご家族がどのような選択をするかについて、様々な思いがあると思います。
ご本人の意思の尊重:延命治療を行うかどうかなど、本人の希望に基づいて支援することが一番重要です。健康なうちから、もしもの時にどうしたいか話し合っておくのも良いでしょう。
医師や看護師との相談:最適な対応を見つけるために、医療チームと十分に話し合うことが大切です。
「何もしない」という選択:無理に栄養補給を行わず、静かに見守るという選択肢もあります。これは「何もしない」のではなく、ご本人の意思を尊重した立派な選択肢です。