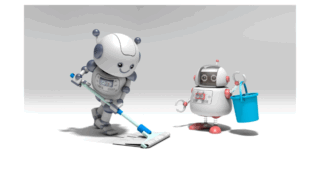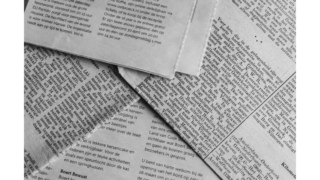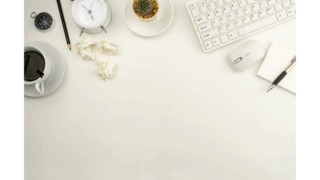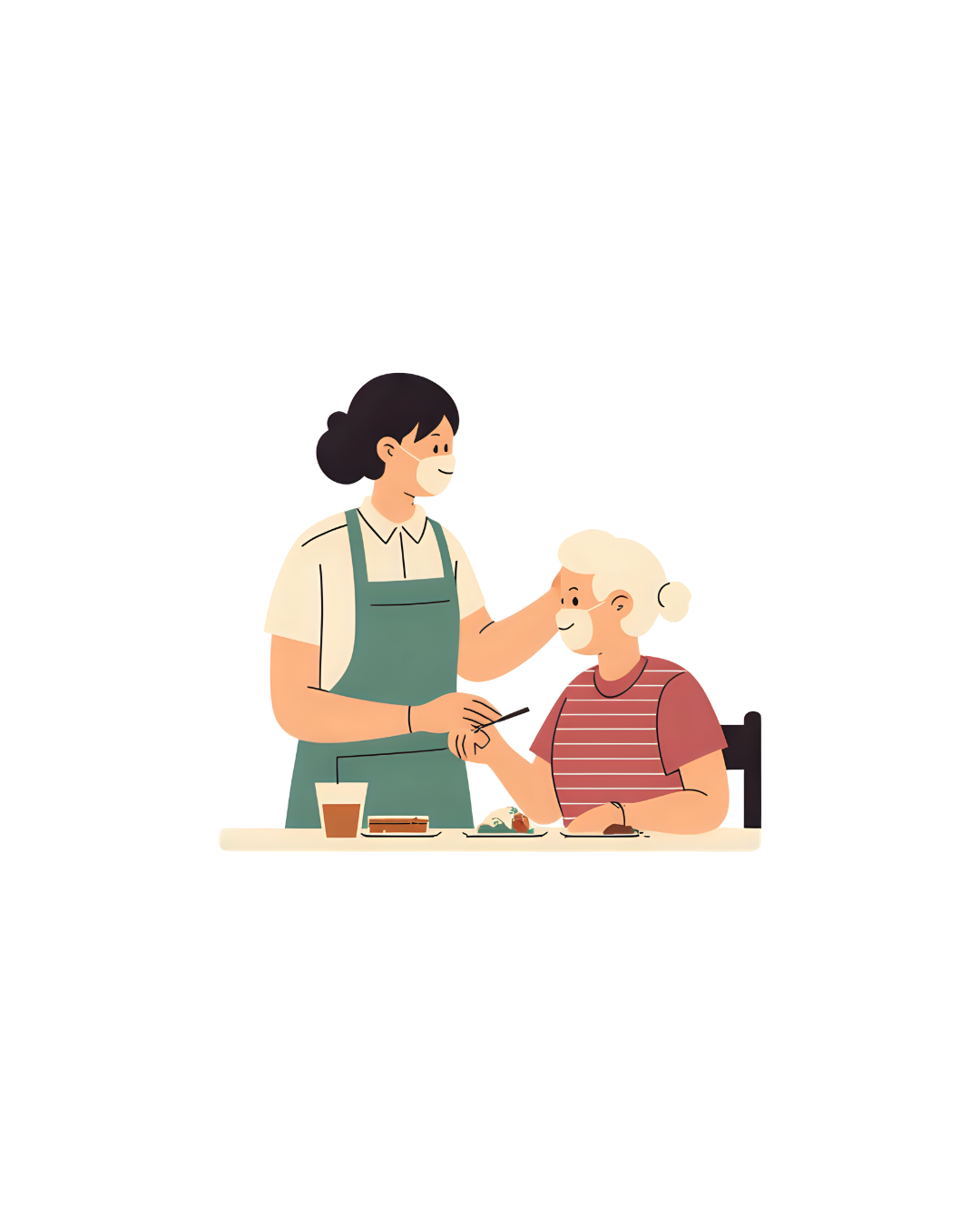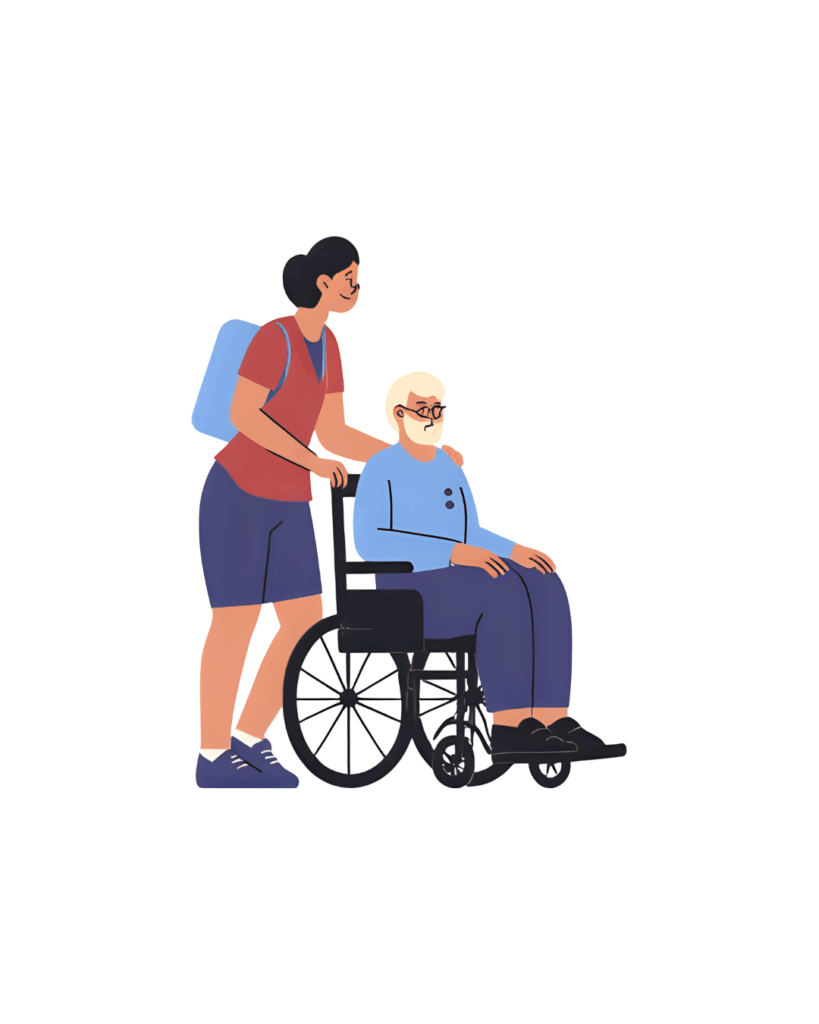
介護保険で利用できるサービスはいくつもの道筋があり、要介護者の状態や生活環境に応じて選択できます。大きく分けて、以下の3つのサービス体系があります。
在宅(居宅)サービス
在宅で生活しながら支援を受けられるサービスです。訪問介護や通所介護など、利用者が自宅で安心して生活を続けられるようにサポートします。
訪問サービス
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や、掃除、洗濯、買い物などの生活援助を行います。訪問看護や訪問リハビリテーションも含まれます。
- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 訪問入浴介護
通所サービス
通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーション(デイケア)のように、施設に通って食事、入浴、レクリエーション、機能訓練などを受けるサービスです。
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 小規模多機能型居宅介護
- お泊りデイサービス
短期入所サービス(ショートステイ)
介護者が一時的に介護できない場合に、施設に短期間入所して生活援助や機能訓練を受けるサービスです。介護者の負担軽減(レスパイトケア)が目的の場合もあります。
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 有料ショートステイ(介護保険適用外)
福祉用具貸与・購入費支給
車椅子や介護ベッドなどの福祉用具のレンタル費用が支給されます。また、入浴補助用具などの特定福祉用具の購入費用も支給の対象となる場合があります。
介護保険の対象となる福祉用具は13品目あり、要介護度に応じて利用できる品目が異なります。
要支援1・2、 要介護1の方が利用できる品目
- 手すり
- スロープ
- 歩行器、歩行補助杖
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
要介護2以上の方が利用できる品目
- 車椅子、車椅子付属品
- 特殊寝台、特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(工事不要のもの)
- 移動支援用具(モーター付き)
- 購入対象の福祉用具
住宅改修費支給
手すりの設置や段差の解消など、自宅を改修する費用が支給されます。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止および移動の円滑化
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- その他これらの住宅改修に付帯して必要となる工事
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホーム、養護老人ホームなどで生活している要介護者に対し、日常生活上の支援や機能訓練を提供するサービスです。
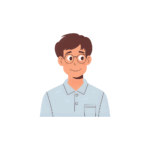
こういった施設は介護保険法上は、居宅と位置付けられているため、居宅サービスに含まれるんです

分かりにくいですね
施設サービス
介護保険制度で定められた施設に入居し、介護を受けるサービスです。原則として要介護3以上の方が主な対象となることが多いです。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人福祉施設とは、在宅での生活が困難な要介護者が入所し、日常生活の介護や機能訓練などを受けられます。
介護老人保健施設(老健)
介護老人保健施設とは、病院での治療を終えて病状が安定した方が、在宅復帰を目指してリハビリテーションを中心とした医療ケアや介護を受ける施設です。
介護医療院
介護医療院とは、長期にわたる療養が必要な方が、医療と介護を一体的に受けられる施設です。
地域密着型サービス
住み慣れた地域で生活を継続できるように、地域に密着した小規模な施設や事業所で提供されるサービスです。住民票のある市区町村内の事業者しか利用できないのが特徴です。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活を送りながら、介護やリハビリテーションを受けます。
小規模多機能型居宅介護
利用者の状態に合わせて「訪問」「通い」「宿泊」のサービスを組み合わせて利用できます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中に複数回の訪問や、夜間の緊急時に対応するサービスです。
これらのサービスを利用するには、まず要介護認定(要支援1~2、要介護1~5)を受ける必要があります。要介護度や住んでいる地域、サービス事業所によって利用条件や費用が異なりますので、詳細は地域包括支援センターやサービス事業者に確認することが重要です。

上記のサービスに以外にもさまざまな形態があり、具体的にどういうところなのか?何をしてくれるのか?分からない方も多いと思います。詳しくは後ほど順番に解説していきますね。
緊急で介護が必要になった、調べている時間がない方もいると思います。
そういった場合は、行政の相談窓口を積極的に活用していただければと思います。
地域包括支援センター
よりそいホットライン
こころの健康相談統一ダイヤル
消費者ホットライン
国民生活センター
まずは電話もしくはメールをしてをしてみて下さい。
厚生労働省:困った時の相談窓口