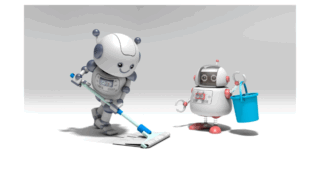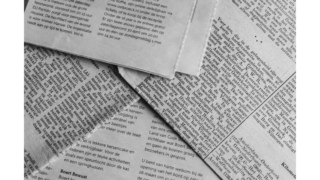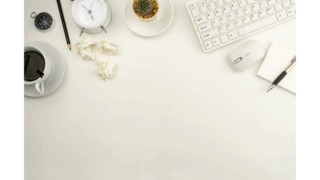ケアマネージャーの役割
- ケアプランの作成
- サービス事業者との連携・スケジュール調整
- 相談対応(本人・家族・事業者のスタッフ・各業者・行政・医療機関など)
- 行政手続きの補助

ケアマネの仕事はとても幅広く、本人や家族の生活を支えるかなめの存在。本人の生活が改善されたり、家族の負担が軽減されたりする場面に立ち会えるため、大きなやりがいがあります。
ケアマネージャーの主な業務
ケアプランの作成と管理
介護を必要とする本人や家族からの相談を受け、抱えている課題を分析し、適切な支援やサービスが受けられるようにケアプラン(介護サービス計画書)を作成します。定期的に利用者の自宅を訪問し、状況の変化を確認しながらケアプランの見直しも行います。
介護保険の給付管理(国から貰えるお金)
利用者が介護保険サービスを利用した際の費用を管理する「給付管理」も重要な業務です。ケアマネージャーは、介護サービス提供事業者がサービスに対して報酬を受け取るために必要な「給付管理票」を作成し、国民健康保険団体連合会(国保連)に提出します。
関係機関との連絡調整
介護サービスを提供する事業者や自治体、医療機関などと利用者との間に入り、連絡調整を行います。利用者が入院した場合は、医療機関と連携して退院後の介護サービスの調整も行います。
要介護認定に関する業務
利用者が介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。ケアマネージャーは、この要介護認定の申請代行や、認定調査に立ち会ったり、聞き取りを行うこともあります。また、利用者の状態に変化があった際の区分変更(もう一度認定をやり直す)申請や更新(保険適用期間を延長する)手続きも行います。
相談援助と情報提供
介護に関する悩みや相談に乗り、利用者やその家族の要望に合った介護サービスの情報を提供します。利用者が施設への入所を検討している場合には、施設の紹介や入所のサポートを行うこともあります。生活保護申請の補助や配食サービスの紹介など、幅広い生活支援も行います。

もしケアマネさんが見つからなかったらどうなるの?
ケアマネージャーがいない場合の対応策
ケアマネージャーと契約できない場合
1. 市町村の介護相談窓口への相談
住んでいる地域の市町村の介護相談窓口に相談します。市町村はケアマネージャーが所属する居宅介護支援事業所の許認可・指導を行っており、新しい事業所の情報や他市町村の状況など、ケアマネさんを見つけるアドバイスをもらえます。

ハートページという資料(事業所の名称や連絡先、ケアマネージャーの人数などが載っている)がもらえると思います
2. サービス提供事業者への直接相談
希望するサービスを提供している事業者に直接相談することも可能です。事業者がケアプラン作成の相談に応じてくれる場合があります。
3. 身近な支援ネットワークや地域のサービスの活用
地域には、さまざまな形で高齢者支援を行っている団体やサービスがあります。地域の社会福祉協議会やボランティア団体などに相談し、支援ネットワークを活用することも有効です。
4. 医療保険サービスの利用
介護保険サービスとは異なりますが、医療保険が適用される訪問看護や訪問リハビリテーションなど、病気や状態によっては利用できるサービスもあります。
5. セルフケアプラン(自己作成)の作成
自己負担は増えますが、利用者自身でケアプランを作成することも可能です。ただし、この場合、必要な書類の準備や介護保険の複雑な仕組みを理解する必要があり、大きな負担となります。ケアマネージャーに依頼する場合と異なり、専門知識に基づいた最適なケアプラン作成が難しい点や、作成費用がかからないというメリットよりも、かなりの手間と労力のデメリットの方が上回る現状があります。

セルフプランの認知度はまだまだ低く、市区町村の窓口で相談すると「難しい」「ケアマネージャーに依頼した方がいい」といった反応をされることがあります
ケアマネージャー不足の背景
ケアマネージャーが不足している背景には、少子高齢化による需要の増加に加え、ケアマネージャーの業務負担の大きさや給与待遇の問題などが挙げられます。特に、2024年の介護報酬改定では、居宅ケアマネージャーが担当できる利用者の人数に関する条件が緩和されたものの、ケアマネージャーの処遇改善加算については触れられておらず、依然として課題が残されています。
ケアマネージャーの種類
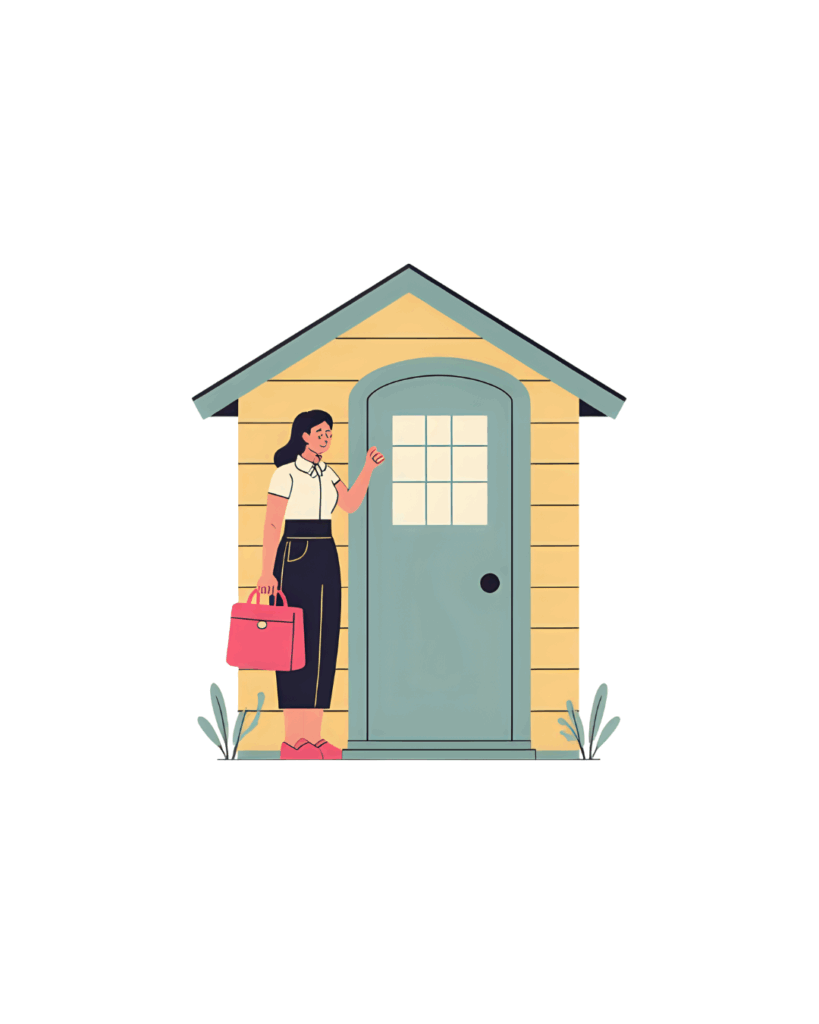
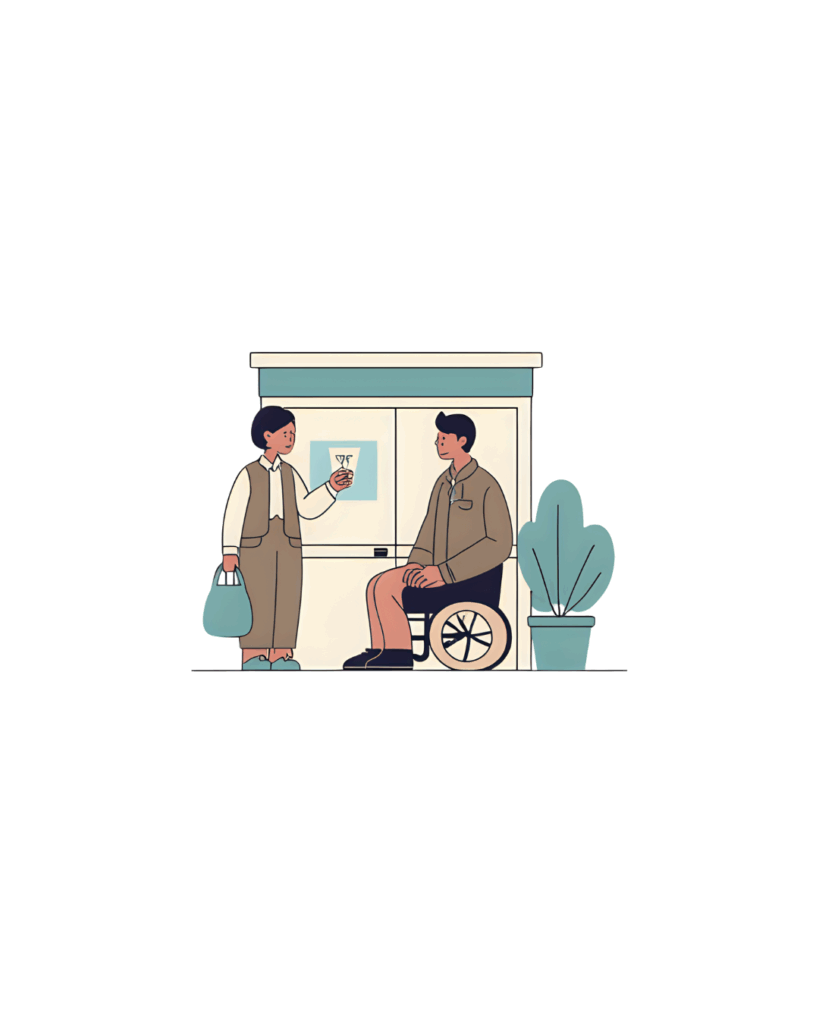
ケアマネージャーは、介護を必要とする方々が自立した生活を送るためのサポートを行う、介護保険のスペシャリストと言われています。