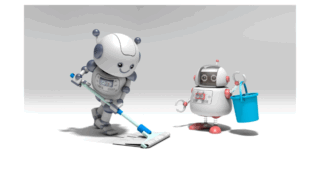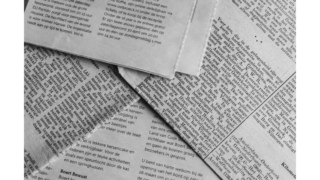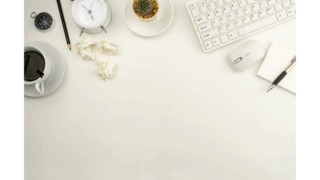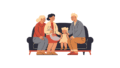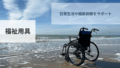要介護の原因は「認知症」が2割
介護や支援が必要となった主な原因としては、「認知症」が最も多く23.6%となっています。 次いで「脳血管疾患(脳卒中)」19.0%、「骨折・転倒」13.0%、「高齢による衰弱」13.2%、「関節疾患」10.2%となっています。
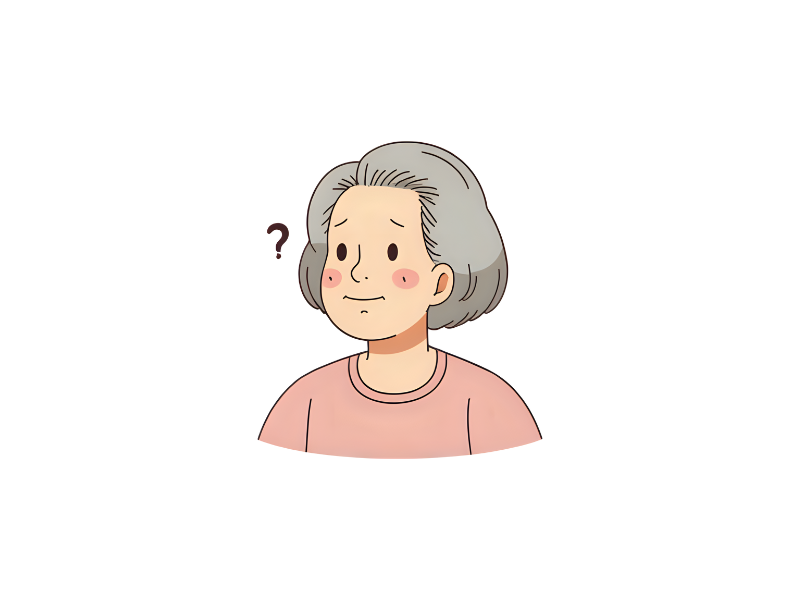
1位 認知症

2位 脳血管疾患

3位 骨折・転倒
ケアマネージャーは要介護認定の原因疾患の上位、あるいは高齢者に多い疾患群に着目し、疾患に特有な病態や症状の視点、回復や改善、もしくは進行を緩やかにする可能性が想定される支援として、以下の5つの病気に対し、より専門性をもってプラン作成に取り組んでいます。
これらは生活習慣病(糖尿病や心臓病などメタボリックシンドロームとの関連が深いもの)が背景にあることもあります。
要支援と要介護別の原因
要支援者: 「関節疾患」が最も多い原因となっています。
要介護者: 「認知症」が最も多い原因となっています。特に、要介護1の認定者の26.4%が認知症を原因としています。
男女別の原因
男性: 「脳血管疾患(脳卒中)」が最も多い原因で、全体の24.5%を占めます。悪性新生物(がん)も男性の要介護の原因として大きな割合を占めることがあります。
女性: 「認知症」が最も多い原因で、全体の19.9%を占めます。また、「骨折・転倒」も女性で要介護状態になる原因として、男性よりも高い割合(14.9% vs 6.7%)を示しています。
その他の原因
高齢による衰弱:加齢による心身機能の衰弱も、介護が必要になる大きな要因です。
サルコペニア(筋肉量の減少):低栄養状態と運動量の低下が筋肉量の減少を引き起こし、要介護状態につながることもあります。
要介護状態とは、一時的な症状ではなく、6ヶ月以上継続して日常生活に介護が必要と見込まれる状態を指します。これらの原因を理解することは、要介護状態の予防や対策を考える上で重要です。
老化予防の研究は近年急速に進展しており、「老化は病気であり、治療や予防ができる」という考え方が広まってきました。「老化を遅らせる」だけでなく、「老化を治療する」時代が訪れようとしています。