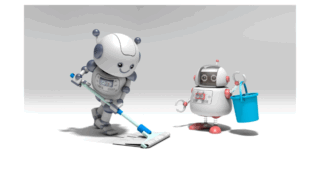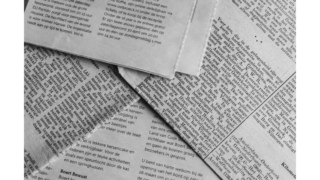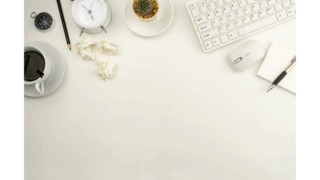介護福祉士は、介護分野で唯一の国家資格であり、身体や精神に障害があるなど、日常生活を送ることが困難な方々に対し、専門的な知識と技術を用いて生活全般の支援を行う専門職です。
主な業務内容
介護福祉士の仕事は、体を動かす身体介護が中心です。利用者の日常生活をサポートするため、食事、入浴、排泄の介助、移動・移乗の介助など、多岐にわたる身体的なケアを行います。
身体介護の具体例
介護福祉士が利用者の身体に直接触れて行う介護には、以下のようなものがあります。
食事介助:食事が困難な利用者への食事のサポート。
入浴介助:利用者のお風呂の手伝い。
排泄介助:トイレの介助やおむつ交換など。
着替え介助:衣服の着脱のサポート。
移動・移乗介助:車椅子への乗り降りや室内での移動、外出時のサポート。
身体整容:洗顔や歯磨きなど身だしなみを整える手伝い。
働く場所による仕事内容の違い
介護福祉士は、特別養護老人ホーム、デイサービス、訪問介護など、様々な場所で働きます。勤務先によって仕事内容の重点が異なりますが、どこで働く場合でも身体を動かす業務は含まれます。
特別養護老人ホーム:要介護度が高い利用者が多く、身体介護の頻度が高い傾向にあります。
デイサービス:レクリエーションや機能訓練など、利用者の社会参加や身体機能維持を目的とした活動も行います。
訪問介護:利用者の自宅を訪問し、身体介護だけでなく家事援助も行います。
その他の多様な業務
身体介護以外にも、介護福祉士は以下のような専門的な業務も担当します。
生活援助:掃除、洗濯、調理など、家事全般のサポートです。
相談・助言:利用者やその家族からの介護に関する相談に対応し、アドバイスを行います。
社会活動支援:就労支援や地域活動の情報提供など、利用者が社会とのつながりを保てるようサポートします。
チームマネジメント:他の介護職員への指導や教育、介護サービスの質の管理など、リーダーとしての役割も期待されています。
介護福祉士になるには、介護福祉士国家試験に合格する必要があります。受験資格には、実務経験ルート、養成施設ルート、福祉系高校ルートなどがあります。介護福祉士の資格を持つことで、専門知識やスキルが身につき、給与の向上やキャリアアップ、転職・就職に有利になるなどのメリットがあります。
介護士という言葉は介護業務に従事する人全体の総称ですが、介護福祉士はその中でも国家資格を持つ人を指します。
人との関わりから得られる魅力
感謝の言葉と笑顔 介護福祉士の仕事は、利用者の方々やそのご家族から「ありがとう」「助かった」と直接感謝の言葉をいただける機会が多いのが特徴です。利用者の笑顔を見たり、回復したりしていく姿を見ることは、大きなやりがいにつながります。
社会貢献の実感 高齢化が進む社会において、介護福祉士は重要な役割を担っています。人手不足の介護業界を支える一員として、誰かの役に立っているという充実感を得られるのは大きな魅力です。
人生の先輩から学ぶ機会 日々のコミュニケーションを通じて、利用者のこれまでの経験や価値観を理解し、その方らしい生活をサポートできることも魅力です。
キャリアと専門性の魅力
国家資格としての安定性 介護福祉士は介護分野で唯一の国家資格であり、生涯使える資格です。専門性の高い知識と技術を持つ人材として需要が高く、将来性も期待できます。
キャリアアップの可能性 資格取得後は、現場のリーダーや主任など、重要な仕事を任される機会が増えます。スタッフの指導や教育、研修の企画など幅広い業務経験を積むことで、管理者へのキャリアアップも可能です。
多様な働き方と活躍の場 介護福祉士は、特別養護老人ホームやデイサービスだけでなく、障がい者施設、病院、行政機関など、多岐にわたる場所で活躍できます。求人も豊富で、自分に合った働き方を見つけやすいというメリットもあります。また、資格手当による収入アップも期待できるでしょう。
深刻な人材不足と労働環境
日本は世界でも類を見ない速さで高齢化が進んでおり、これが介護福祉士不足の大きな背景となっています。

介護ニーズの増大 2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、介護を必要とする方の数が急増します。2026年度には約240万人、2040年には約272万人の介護職員が必要とされていますが、2023年時点では約212万人しかおらず、2026年には約28万人もの介護職員が不足すると推計されています。
生産年齢人口の減少 少子化により、介護を担う若い世代の人口が減少しています。介護サービスの需要は高まる一方で、働き手が減っているため、需給バランスが崩れています。
介護現場では、利用者数の増加に反して、人材不足が深刻化しています。
人手不足の現状 介護職員の有効求人倍率は高く、多くの施設で必要なスタッフ数を確保できていないのが現状です。人手不足は、介護サービスの質の低下や、職員一人あたりの業務負担増大につながり、離職に拍車をかける悪循環を生んでいます。
労働環境の問題 介護職は「きつい・汚い・危険」に「給料が安い」を加えた「4K」と評されることがあります。体力的な負担が大きい業務が多く、腰痛など身体への影響も少なくありません。また、他産業に比べて平均年収が低い傾向にあることも、人材が定着しない要因の一つと考えられています。
介護職員の高齢化 介護職員自体の高齢化も進んでおり、身体的負担の大きい業務を続けることが困難になるケースもあります。
介護サービスの質の維持・向上
人手不足が続く中で、サービスの質を維持・向上させることも大きな課題です。
ケア不足や虐待のリスク 職員の数が足りないことで、利用者への十分なケアが行き届かなかったり、ストレスから虐待へとつながるリスクも指摘されています。
施設の倒産と介護難民 人手不足や経営難により、施設の倒産が増加傾向にあり、その結果、介護を受けたくても受けられない「介護難民」が増える可能性もあります。
業務改善とICTの活用 限られた人員で質の高いサービスを提供するためには、業務の効率化や生産性向上が不可欠です。ロボット・センサー・ICTといったテクノロジーの活用が期待されています。
キャリアアップに役立つ資格
日本介護福祉士会が定める「軸となる研修」
日本介護福祉士会は、介護福祉士の専門性を高めるための生涯研修体系を定めています。主な研修は以下の3つです。
介護福祉士基本研修:資格取得後から実務経験2年未満の介護福祉士を対象としており、質の高い介護の実践力を培うことを目的としています。
ファーストステップ研修:実務経験2~3年の介護福祉士向けで、小規模チームのリーダーや新任職員の指導係を育成する目的があります。
認定介護福祉士養成研修:介護福祉士の上位資格である「認定介護福祉士」を目指すための研修です。地域における介護実践の展開や多職種連携、チームマネジメントなど、幅広い知識と技術を習得します。2025年度も全国の介護福祉士会で開講が予定されています。
介護福祉士の資格をお持ちの方が、さらに専門性を高めたり、活躍の場を広げたりするための研修や資格は多数あります。
専門性を深める研修
介護福祉士実務者研修:介護福祉士国家試験の受験には必須の研修であり、利用者へ質の高いサービスを提供するための幅広い知識と技術を習につけます。医療的ケアに関する内容も含まれています。
喀痰吸引等研修:特定の医療行為(痰の吸引や経管栄養など)ができるようになるための研修で、基本研修と実地研修があります。
認知症介護実践者研修:認知症の利用者に対する専門的なケアを学ぶ研修です。
重度訪問介護従業者養成研修:重度の障害がある方への介護知識や対応方法を学ぶ研修で、訪問介護の仕事の幅を広げることができます。
同行援護従業者養成研修:視覚障害のある方の外出を支援するガイドヘルパーの資格を取得するための研修です。
行動援護従業者養成研修:知的障害や精神障害のある方の行動をサポートするための研修です。
職能的研修・施設向け研修
多職種連携等に関する研修:他の専門職との連携を円滑にするスキルを身につけます。
介護過程の展開を強化する研修:個別ケアの計画と実践に関する専門性を高めます。
災害ボランティア基本研修:災害時における介護支援の知識とスキルを習得します。
地域共生社会に関する研修(旧:障がい領域研修):地域での共生を支援するための知識を深めます。
サービス提供責任者研修:訪問介護事業所などで、サービス計画作成やヘルパー指導を行うための研修です。
介護施設向け研修:管理職向け、リーダー向け、一般職員向けなど、階層別やテーマ別に様々な研修があります。リスクマネジメント、ハラスメント、コミュニケーション、メンタルヘルスなど多様な内容があります。
これらの研修を通じて、介護福祉士は自身のスキルアップやキャリアアップを実現し、より質の高い介護サービスの提供に貢献することができます。
その他のキャリアアップに繋がる研修・資格
認定介護福祉士
介護福祉士の上位資格として注目されているのが認定介護福祉士です。2015年に認証・認定が始まった比較的新しい資格で、取得者はまだ少ないですが、介護福祉士よりも広範囲の知識やスキルを習得できます。高品質なサービス提供、現場の教育・指導、地域マネジメントなど、高度な専門性を活かして活躍できるようになります。
ケアマネジャー(介護支援専門員)
ケアマネジャーは、利用者や家族の状況に合わせてケアプランを作成し、介護サービス事業者との連絡調整を行う専門職です。介護福祉士としての実務経験を積むことで、受験資格が得られます。日中の業務が中心で介護業務がないため、体力的な負担を減らしたい方にもおすすめのキャリアパスです。
社会福祉士
社会福祉士は、精神保健福祉士と並び、福祉に関する国家資格です。主に、福祉施設や病院で、身体的または精神的なハンディキャップを持つ人々の相談に応じ、社会生活を支援する役割を担います。介護福祉士の経験を活かし、相談援助の専門家として活躍できます。
看護師
介護福祉士から看護師の資格取得を目指すことも可能です。看護師は国家資格であり、介護福祉士だけでは行えない医療行為ができるようになります。介護施設だけでなく、病院での勤務も可能となり、働く場所の選択肢が大きく広がります。
精神保健福祉士
精神保健福祉士は、精神疾患を抱える方への支援や社会復帰をサポートする国家資格です。介護の現場でも精神面に配慮したケアの重要性が増しており、この資格を取得することで活躍の場が拡大します。
介護福祉士ファーストステップ研修
介護福祉士として実務経験2年以上の方を対象とした研修で、小規模チームのリーダーや新人の指導係となる人材を育成することを目的としています。この研修を修了することで、チームリーダーとしての知識やスキルが身につき、キャリアアップにつながります。
役職でのキャリアアップ
介護福祉士の資格があれば、以下のような役職へのキャリアアップも可能です。
サービス提供責任者:訪問介護事業所で、利用者へのサービス計画の作成やヘルパーの指導・管理を行うリーダー的な役割です。
生活相談員:特別養護老人ホームやデイサービスなどで、利用者や家族の相談に応じ、関係機関との連携を担います。
介護主任・介護長・施設長:施設の管理職として、介護サービスの質の向上や職員のマネジメント、施設運営全般に携わります。
介護予防運動指導員養成研修
介護予防運動指導員は、高齢者の自立した生活をサポートするための運動指導や介護予防プログラムの作成を行う専門職の資格です。地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターが認定する民間資格で、研修を修了し試験に合格することで取得できます。
受講資格と内容
この研修の受講には、以下のいずれかの資格を持っていることが条件となります。
・介護職員初任者研修修了者で実務経験2年以上
・介護福祉士実務者研修修了者
・介護支援専門員
・介護福祉士、看護師、理学療法士、作業療法士などの医療・福祉系の国家資格保有者
カリキュラムは合計31.5時間から33時間で、高齢者の筋力トレーニングや転倒予防、失禁予防といった身体面の知識に加えて、認知症やうつ、閉じこもりに関する知識も幅広く学べます。eラーニングでの受講も可能です。受講費用は6万円から9万円程度が相場とされています。
修了試験と更新
研修の最後には修了試験がありますが、講習内容をしっかり理解していれば合格できるレベルであり、合格率は90%以上と予想されています。万が一不合格でも、初回受験日から1年以内であれば再受験が可能です。この資格は3年ごとの更新が必要です。
介護予防ケアマネジメントオンデマンド研修
一般財団法人長寿社会開発センターでは、適切な介護予防ケアマネジメント手法の普及を目的とした「介護予防ケアマネジメントオンデマンド研修」を提供しています。この研修では、自立支援の考え方や介護保険制度の基本理念、介護予防ケアマネジメントの具体的な過程について学ぶことができます。
介護施設における必須研修
介護施設では、「介護予防及び要介護度進行予防に関する研修」が必須研修の一つとされています。これは、介護が必要な状態の発生を防ぎ、すでに介護が必要な状態であってもその悪化をできる限り防ぐことを目的としたものです。この研修では、高齢者の転倒予防に関する内容も扱われます。
これらの研修を通じて、介護福祉士は介護予防の専門知識と技術を習得し、利用者の自立支援と生活の質の向上に貢献することが期待されています。