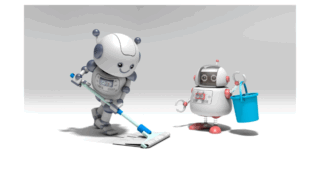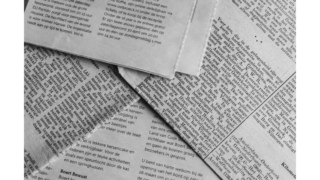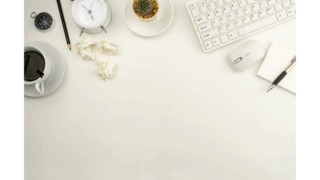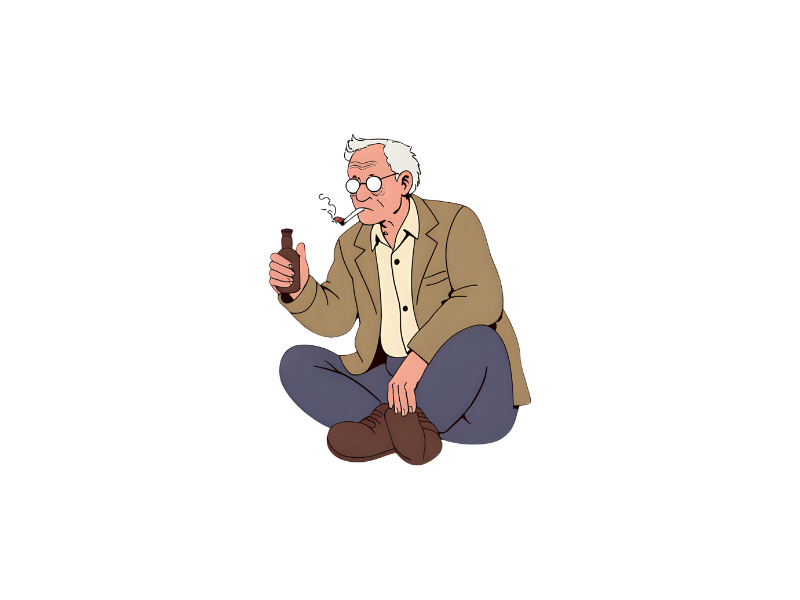
高血圧と心疾患が引き起こす問題
高血圧や心疾患は、加齢とともに重症度が増しやすく、様々な健康上の問題を引き起こすことで、最終的に介護が必要となる大きな要因となります。これらの疾患は、脳卒中や認知症、腎臓病などの合併症を引き起こし、身体機能や認知機能の低下を招くことがあります。
高血圧が引き起こす合併症
高血圧は心臓に負担をかけ、血管を傷つけることで、以下のような様々な合併症を引き起こします。
脳卒中: 高血圧は脳の血管に大きな負担をかけ、脳出血や脳梗塞のリスクを高めます。これにより、麻痺や言語障害、嚥下障害などが残ることがあり、日常生活に大きな支障をきたし、介護が必要となる原因となります。
心臓病: 高血圧は心臓肥大や心不全を引き起こし、心臓の機能が低下します。これにより、息切れやむくみ、倦怠感などが現れ、活動が制限されることで介護が必要になることがあります。
認知症: 長期間の高血圧は、脳の細い血管にダメージを与え、認知症(特に血管性認知症)のリスクを高めることが知られています。認知機能の低下は、身の回りのことができなくなる原因となり、介護に繋がります。
腎臓病: 高血圧は腎臓の細い血管を傷つけ、腎機能の低下を招きます。最終的に腎不全に至ると、透析治療が必要となり、QOL(生活の質)が著しく低下し、介護が不可欠となる場合があります。
高齢者に多い心臓病
社会の高齢化に伴い、高齢者の方々に見られる心臓病の数も増えています。特に、心不全、虚血性心疾患(心筋梗塞や狭心症)、心臓弁膜症は高齢者に多く見られる病気です。
心不全
心不全は、心臓のポンプ機能が低下し、全身に必要な血液を十分に供給できなくなる状態を指します。これは特定の病気の名前ではなく、さまざまな心臓病の結果として起こる「症候群」です。高齢者の心不全患者は全国で約120万人と推計されており、2030年には130万人にも達すると予測されています。
高齢者の場合、息切れや疲労感などの症状があっても、「年のせい」だと思い込んで放置してしまうことが少なくありません。心不全が進行すると、これまでできていたことが急にできなくなったり、体力が落ちたりすることがあります。
虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)
虚血性心疾患は、心臓に血液を送る冠動脈が狭くなったり詰まったりすることで、心臓の筋肉(心筋)への血液供給が不足する病気です。
狭心症: 冠動脈が狭くなることで、心筋への血液供給が一時的に不足し、胸の痛みや圧迫感が生じます。初期症状として、疲れやすさやだるさ、運動時の息切れなどがあります。進行すると、安静時にも胸痛や息苦しさが出ることがあります。
心筋梗塞: 冠動脈が完全に詰まり、心筋の一部が壊死してしまう状態です。激しい胸の痛みに襲われることが多いですが、下顎や肩、みぞおちの痛みとして現れることもあります。最大の危険因子は動脈硬化です。
心臓弁膜症
心臓弁膜症は、心臓にある弁がうまく機能しなくなる病気です。弁が硬くなって開きにくくなったり(狭窄症)、うまく閉じなくて血液が逆流したり(閉鎖不全症)といった問題が起こります。
高齢者では、加齢に伴う弁の変性や石灰化によるものが多いとされています。65歳以上の約10人に1人が心臓弁膜症を患っていると言われています。初期症状は疲れやだるさ、息切れですが、進行すると心不全に至る可能性があります。
その他の心臓病
高血圧: 高齢者の高血圧は年齢とともに増加します。動脈硬化などが原因となり、脳卒中や腎不全、狭心症、大動脈瘤などの合併症を引き起こします。
不整脈: 心臓の拍動リズムが乱れる状態です。特に「心房細動」は、高齢者に多く見られる不整脈で、これ自体が心不全の原因となることもあります。半数近くの人は自覚症状がないため、定期的な脈拍チェックが重要です。
これらの心臓病は、最終的に心不全を引き起こす可能性があります。高齢者の心不全は症状がはっきり現れにくく、「年のせい」と見過ごされがちですが、早期発見と治療が重症化を防ぐ鍵となります。
心疾患をうたがう症状
心疾患は、早期に発見して適切な治療を受けることが非常に重要です。体の不調が心臓からのSOSサインであることも多いので、以下のような症状には特に注意しましょう。
息切れ・呼吸困難
階段や坂道を上る際に息切れがひどくなったり、少し動いただけでも息苦しさを感じたりする場合は、心臓の機能が低下している心不全や、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)、心筋症、弁膜症などの可能性があります。病状が進行すると、夜間に呼吸が苦しくなって目が覚める「夜間呼吸困難」や、横になっているよりも体を起こして座っている方が楽な「起坐呼吸」といった症状が現れることもあります。
動悸
胸がドキドキする、脈が飛ぶ、脈が速い・遅い、胸に一瞬違和感があるなど、急に起こってすぐ治まる症状は、不整脈の典型的なサインかもしれません。不整脈には「期外収縮」のように健康な人でも起こるものも多いですが、心房細動や心室頻拍など、治療が必要な不整脈もあります。
痛み(胸・背中・のど・腕)
胸や背中の痛みは、心臓病で最も多くみられる症状の一つです。心疾患による痛みは、胸だけでなく肩、腕、のど、首、あごに及ぶこともあり、「放散痛」と呼ばれます。締め付けられるような圧迫感や重いものが乗っているような感覚、鋭い痛みなど、痛みの感じ方は様々です。これは狭心症や心筋梗塞、心膜炎、大動脈解離などの可能性があり、命に関わることもあるため、胸痛を感じたら早めに医療機関を受診してください。特に、運動時や精神的ストレスを感じたときに症状が出やすく、数分間続くことが多いですが、安静にすると和らぐ場合は狭心症が疑われます。一方で、20分以上痛みが続く場合は心筋梗塞の可能性も考えられます。
むくみ
手足や顔がむくむ「浮腫」も、心不全の症状として現れることがあります。特に足のむくみは、心臓のポンプ機能が低下して血液を全身に十分に送れなくなり、水分が体に溜まることで起こります。
その他の注意すべき症状
失神: 一時的に意識を失うことがあります。
疲れやすい・だるい: 日常的に疲労感が強く、だるさを感じる場合は、心不全など心臓の機能低下の可能性があります。特に、以前よりも疲れやすくなったと感じたら注意が必要です。
手足の冷え: 血流が悪くなることで手足が冷たくなることがあります。
夜間の尿量増加: 寝ている間に何度もトイレに行くようになるのは、心不全のサインの一つであることがあります。
チアノーゼ: 唇などが青紫色になる状態。非常に危険な状態なので、すぐに医療機関を受診してください。
もの忘れが多くなった: 認知機能の低下は、心不全の症状と関連している場合もあります。
めまい・脱力感・不安感: 狭心症の前兆として、胸の痛み以外にもこれらの症状が現れることがあります。
心疾患の症状は、個人差が大きく、他の病気と間違えやすい場合もあります。特に、糖尿病の患者さんや高齢者では、症状に気づきにくいこともあります。気になる症状がある場合は、自己判断せずに、早めに循環器内科を受診して専門医に相談することが大切です。
高血圧と心疾患の予防について
高血圧と心疾患は、生活習慣病の代表格であり、健康寿命を縮める大きな要因となります。しかし、日々の心がけで予防や改善が可能です。ここでは、特に重要なポイントをいくつかご紹介しますね。
食生活の改善
塩分を控える: 日本人は塩分を摂りすぎる傾向があります。高血圧の予防には、1日の食塩摂取量を6g未満に抑えることが推奨されています。だしや香辛料を上手に活用して、美味しく減塩を心がけましょう。
カリウムを積極的に摂る: カリウムは余分なナトリウム(塩分)を体外に排出する働きがあります。野菜や果物に多く含まれているので、積極的に摂取しましょう。
飽和脂肪酸の摂取に注意: お肉や乳製品などの動物性脂肪に多い飽和脂肪酸の摂りすぎは、悪玉コレステロールを増やし、動脈硬化を促進します。
糖質を控えめにする: 糖質の摂りすぎは糖尿病の原因となり、心臓病のリスクを高めます。
野菜と魚を中心にする: 食物繊維や抗酸化物質が豊富な野菜や果物は、虚血性心疾患の予防に効果的です。また、鮭などの青魚に含まれるDHAやEPA(オメガ3脂肪酸)は、血液をサラサラにし、動脈硬化や心疾患の予防に役立つと言われています。
適度な運動
ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、高血圧や心疾患の予防に有効です。可能であれば毎日30分以上、または週に180分以上を目安に行いましょう。無理のない範囲で、ご自身の体力に合わせて継続することが大切です。
禁煙と節酒
禁煙する: 喫煙は血管を収縮させて血圧を上げ、血液の流れを悪くし動脈硬化を引き起こします。たばこをやめるだけで心臓病や脳卒中のリスクを大幅に減らすことができます。受動喫煙にも注意が必要です。
節酒する: アルコールは一時的に血圧を下げることがありますが、毎日多量に摂取すると逆に血圧を上げてしまいます。男性は1日20~30mL、女性は10~20mL以下に制限し、休肝日を設けるなど工夫しましょう。
その他の生活習慣の改善
肥満を解消する: 肥満は高血圧の大きな原因の一つであり、高血圧の予防には肥満の解消が欠かせません。
ストレスを管理する: ストレスは心臓病の危険因子の一つです。ストレスをため込まず、自分なりの解消法を見つけることが大切です。
十分な睡眠をとる: 睡眠不足は交感神経を刺激し、血圧を上げやすくします。良質な睡眠を心がけましょう。
定期的な健康チェック: 自覚症状がなくても血圧は高くなることがあります。家庭での血圧測定を習慣にし、定期的に健診を受けることで、ご自身の血圧や心臓の状態を把握することが重要です。
内服薬の重要性について
高血圧や心疾患は、放置すると脳卒中や心筋梗塞、心不全、腎臓病など命にかかわる重篤な病気を引き起こす可能性があります。そのため、医師から処方された薬をきちんと服用することは、これらの合併症を予防し、健康な生活を長く続けるために非常に大切です。
薬による血圧管理の必要性
高血圧は、多くの場合、自覚症状がほとんどありません。しかし、症状がないからといって治療せずにいると、知らず知らずのうちに血管にダメージを与え、様々な合併症のリスクを高めてしまいます。生活習慣の改善だけでは血圧が十分に下がらない場合、または合併症のリスクが高い場合には、薬による治療が必要となります。薬で血圧を適切にコントロールすることは、合併症の発症や進行を防ぐ上で欠かせません。
心疾患の薬物療法とは
心疾患の薬物療法は、息切れやむくみなどの症状を改善することと、心疾患の進行を防ぎ、生命予後を改善することの二つの大きな目的があります。心臓のポンプ機能が低下した心不全では、利尿薬で体内の余分な水分やナトリウムを排出し、むくみや息切れを和らげます。また、ACE阻害薬、ARB、β遮断薬、アルドステロン拮抗薬といった薬は、心臓の機能低下を防ぎ、心不不全の進行を抑える効果が証明されています。
副作用とその対策
どんな薬にも副作用は存在します。高血圧治療薬では、めまい、ふらつき、頭痛、動悸、咳、むくみ、便秘、吐き気、発疹など様々な症状が現れることがあります。特に降圧作用の強い薬を飲み始めたばかりの頃は、立ちくらみが起こりやすいので注意が必要です。心臓病の薬は、心臓に直接作用するため、薬が効きすぎた場合には心拍数が過度に少なくなったり、血圧が下がりすぎたりすることがあります。
しかし、心配なからといって自己判断で薬の服用を中止することは非常に危険です。急激な血圧の上昇(リバウンド現象)を引き起こし、脳出血や心筋梗塞などの重篤な合併症のリスクを高める可能性があります。
もし副作用と思われる症状が出た場合は、迷わず医師や薬剤師に相談してください。薬の種類や量を調整することで症状が改善することもあります。
継続することの重要性
高血圧や心疾患の薬は、症状が改善したからといってすぐにやめるものではありません。一時的に血圧が下がったからといって中止すると、血圧が再び上昇し、血管にダメージを与えることにつながります。毎日同じ時間に薬を服用し、飲み忘れた場合でも自己判断でまとめて飲まず、医師の指示に従うようにしましょう。
薬は、高血圧や心疾患による重篤な合併症を防ぎ、あなた自身の健康を守るための大切なツールです。医師や薬剤師と連携し、正しく薬を服用することで、安心した生活を送ることができます。
医師・薬剤師に相談するべき理由
血圧のお薬を飲み忘れた場合は、「医師」や「薬剤師」に相談するのが一番安心で確実です。お薬の種類や、いつ飲み忘れたかによって対応が変わるため、自己判断せずに専門家に相談しましょう。
薬の種類と飲み合わせによる影響
血圧のお薬には様々な種類があり、それぞれ作用や効果の持続時間が異なります。また、他の薬との飲み合わせによっては、薬の効果が強くなりすぎたり、弱まったりすることがあります。例えば、カルシウム拮抗薬という種類の降圧剤は、グレープフルーツジュースと一緒に飲むと作用が強く出すぎてしまい、血圧が下がりすぎる可能性があります。
副作用のリスク回避
もし飲み忘れたからといって、2回分を一度に服用してしまうと、薬が効きすぎてしまい、めまいや転倒などの副作用が生じるリスクがあります。特に血圧が下がりすぎると危険な場合もあるため、正確な指示を仰ぐことが重要です。
飲み忘れを防ぐためのヒント
お薬手帳の活用
お薬手帳には、現在服用しているすべてのお薬の情報が記録されています。他の医療機関を受診する際や、市販薬・サプリメントを使用する際にも、必ず医師や薬剤師に提示し、飲み合わせの確認をしてもらいましょう。
家庭血圧の測定
普段から家庭で血圧を測定し、ご自身の血圧の状態を把握しておくことは、飲み忘れた際の判断材料になったり、医師への相談時に役立ったりします。
決まった時間に服用する習慣
多くのお薬は1日1回の服用で翌日まで効果が持続しますが、生活の中で服用する時間を決め、習慣化することで飲み忘れを防ぎやすくなります。もし、飲み忘れが頻繁に起こるようであれば、薬剤師に相談して一包化(1回分ずつ分包してもらうこと)を検討するのも良いでしょう。
血圧測定の注意点
ご家庭で血圧を正確に測ることは、高血圧の早期発見や日々の管理において非常に重要です。正しい測定方法を知ることで、より信頼性の高い数値を得ることができます。
測定のタイミングと回数
血圧は1日の中で変動するため、毎日同じ時間に測ることが大切です。日本高血圧学会では、原則として朝と夜の1日2回の測定が推奨されています。
朝の測定: 起床後1時間以内、排尿を済ませてから、朝食や降圧剤の服用前に行います。
夜の測定: 就寝前に行います。入浴後30分以上経過し、飲酒直後は避けるようにしましょう。
毎日、朝晩それぞれ2回測定し、その平均値を記録すると良いとされています。
正しい測定姿勢
正確な血圧を測るためには、測定時の姿勢も大切です。
リラックスして座る: 背もたれのある椅子に座り、両足を床につけてリラックスした状態で測りましょう。足を組むと血圧がやや上がることがあるので避けましょう。
カフ(腕帯)の位置: カフは素肌、または薄手の肌着の上から、肘の関節から1~2cm上にぴったりと巻き付けます。
心臓と同じ高さに: 測定する腕(上腕部が推奨されています)は、心臓の高さ(乳頭の位置)と同じになるように机やクッションなどで調整します。
測定中は静かに: 測定中は腕の力を抜き、手のひらを上に向けてリラックスし、話をしたり体を動かしたりしないようにしましょう。
測定機器について
家庭での血圧測定には、上腕式血圧計が推奨されています。心臓に近い位置で測定できるため、より安定した数値が得られやすいです。手首式血圧計はコンパクトで便利ですが、正しい測定には少しコツが必要です。
その他の注意点
体調の良い時に: 入浴後や運動後、喫煙、飲酒の直後は血圧が変動しやすいので避けてください。
毎回記録する: 測定した血圧は、血圧手帳などに記録しておきましょう。継続して記録することで、医師が適切な治療方針を立てる上で非常に役立ちます。
左右の腕で違う場合: 左右の腕で血圧が異なる場合は、高い方の腕で測定するようにしましょう。
白衣高血圧: 病院で測る血圧が高く、家庭で測る血圧が正常な場合は「白衣高血圧」と呼ばれます。しかし、白衣高血圧の人も将来的に高血圧になるリスクがあるため、定期的な検査が重要です。
麻痺がある場合:麻痺のある方が血圧を測定する際は、麻痺のない「健側(けんそく)」で測るようにして下さい。麻痺側の血行が悪く、筋肉が萎縮している可能性があり、それが血圧測定に影響を与えることがあります。
高血圧や心疾患は、生活習慣病であり、一度発症すると完治が難しい病気ですが、日々の適切な管理と生活習慣の改善によって、病気の進行を抑え、合併症を予防し、心臓に優しい生活を送ることができます。
症状の変化に注意
心疾患の症状は、高齢者では「年のせい」と見過ごされがちですが、普段と違う症状や、少し動いただけで息切れがする、足がむくむなどの変化に気づいたら、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。
高血圧や心疾患とうまく付き合っていくためには、これらの生活習慣の改善と、医師や医療従事者との連携が不可欠です。日々の努力が、健康で活動的な生活を送るための基盤となります。