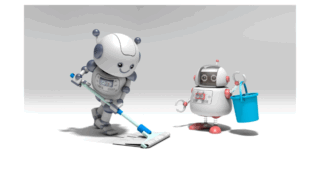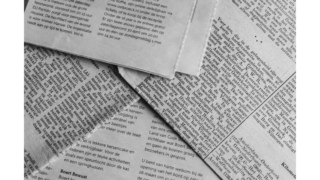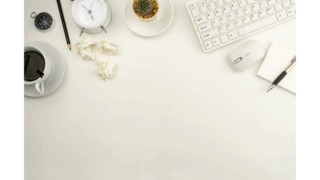通所介護とは、自宅で生活している要介護者が、介護施設などに日帰りで通い、日常生活上の支援や機能訓練などを受けられる介護保険サービスの一つです。一般的に「デイサービス」と呼ばれています。
通所介護の目的
通所介護の主な目的は以下の通りです。
利用者の自立支援と心身機能の維持向上: 食事、入浴、排泄などの日常生活の介助や、リハビリテーション、レクリエーションを通じて、心身の機能維持・向上を図り、利用者の方が可能な限り自立した生活を送れるように支援します。
社会的孤立感の解消と交流の促進: 自宅に閉じこもりがちな利用者の方が施設に通うことで、他者との交流の機会が増え、社会的孤立感を解消し、精神的な活性化を促します。
介護者の負担軽減: 日中、利用者の方が施設で過ごすことで、家族の介護負担を一時的に軽減し、介護者が自分の時間を持てるようにサポートします。
サービス内容
通所介護で提供されるサービスは多岐にわたります。
送迎: 自宅と施設間の送迎サービスがあります。
健康チェック: 血圧や体温測定など、看護師による健康状態の確認を行います。
入浴: 介護職員の介助を受けながら入浴できます。個別の対応や特殊浴槽の利用も可能です。
食事: 管理栄養士が栄養バランスを考慮した食事を提供します。嚥下能力に合わせた食事形態の調整も行われます。
機能訓練: 理学療法士や作業療法士などの専門職の指導のもと、身体機能の維持・向上を目指すリハビリテーションが行われます。集団体操や個別の訓練などがあります。
レクリエーション: ゲーム、手芸、歌、散歩など、楽しみながら心身を活性化させる活動が提供されます。季節ごとのイベントも開催されます。

生活相談: 生活上の悩みや不安について、専門の相談員に相談できます。
利用対象者と費用
利用対象者
原則として、要介護認定で要介護1~5の認定を受けている方が対象です。要支援1・2の認定を受けている方は「介護予防通所介護(地域密着型通所介護)」のサービスを利用します。
費用
通所介護の利用料金は、介護度、利用時間、施設の種類(通常規模型、大規模型など)、サービス内容によって異なります。介護保険が適用されるため、自己負担は原則1割(所得に応じて2割または3割)です。ただし、食費やおむつ代、レクリエーション費などの日常生活費は自己負担となります。
通所介護の種類
通所介護には、大きく分けて以下の3つの種類があります。
通所介護(デイサービス): 一般的な通所介護で、様々な規模の施設でサービスが提供されます。
地域密着型通所介護: 定員が18人以下の小規模な通所介護で、原則として事業所のある市区町村に住む方が利用できます。地域に密着したサービスが特徴です。
認知症対応型通所介護: 認知症の診断を受けている方に特化した通所介護です。認知症の専門知識を持つスタッフが、個々の利用者の症状や状態に合わせたケアを提供し、認知症の行動・心理症状(BPSD)の緩和を目指します。
認知症行動障害との関連
認知症の行動・心理症状(BPSD)とは、中核症状(記憶障害、見当識障害など)に加えて、本人の性格、環境、人間関係などが複雑に絡み合って生じる精神面や行動面の問題です。例えば、徘徊、妄想、幻覚、暴力、暴言、不潔行為、抑うつ、無関心などが挙げられます。
認知症対応型通所介護では、BPSDの理解と対応に重点を置いたケアが提供されます。例えば、徘徊の原因が「今の家が自分の家ではないと思い、昔の家を探している」という見当識障害から来ている場合、無理に止めさせるのではなく、その思いに寄り添い、安心感を提供するようなケアが行われます。
通所介護、特に認知症対応型通所介護は、認知症の方とそのご家族にとって、専門的なケアと介護負担の軽減の両面で非常に重要なサービスと言えるでしょう。
デイサービスは介護保険サービスの一つなので、利用料金は介護度や利用時間、サービス内容などによって決まります。自己負担割合は原則1割ですが、所得に応じて2割または3割になる場合もあります。
デイサービス(通所介護)の費用内訳
デイサービスの費用は大きく分けて以下の3つで構成されます。
介護サービス費(自己負担1〜3割)
これがデイサービスの中心となる費用で、介護保険が適用されます。介護度(要介護1〜5)や利用時間によって料金が変動します。
介護度別: 要介護度が重くなるほど、介護サービス費は高くなります。
利用時間別: 利用時間が長いデイサービスほど、料金が高くなります。
事業所の種類: 通常規模型、大規模型、地域密着型、認知症対応型など、事業所の種類によっても単価が異なります。
加算: 送迎や入浴介助、個別機能訓練、口腔機能向上サービスなど、提供されるサービス内容に応じて様々な加算があります。例えば、入浴介助加算や個別機能訓練加算などが一般的です。
食費(全額自己負担)
デイサービスで提供される昼食やおやつ代は、介護保険の適用外となるため全額自己負担です。施設によって料金は異なりますが、昼食は1食あたり500円〜800円程度、おやつは100円〜200円程度が目安です。
その他の日常生活費(全額自己負担)
介護保険の対象とならない個人的な費用も、全額自己負担となります。
おむつ代: 施設で用意してもらう場合は実費となります。ご自身で持ち込むことも可能です。
レクリエーション費: 施設が企画する特別なイベントや外出にかかる費用などです。
教材費: 趣味活動などで使用する材料費などです。
費用の目安
具体的な月額費用は、地域や利用するデイサービス、介護度、利用頻度によって大きく変わります。例えば、要介護3の方が週に3回、1回あたり7時間以上デイサービスを利用し、食事代やおやつ代を含めると、月に約2万円〜4万円程度が目安となることが多いでしょう。
費用軽減制度
所得が低い方の場合、食費や居住費(短期入所の場合など)について「負担限度額認定」が適用される場合があります。また、医療費控除の対象となる費用もあります。これらの制度を使えるかどうかは、お住まいの市区町村の窓口やケアマネジャーに相談してみると良いでしょう。
デイサービスの費用は事業者やサービス内容によって細かく異なるため、利用を検討する際は、複数の事業所から見積もりを取り、サービス内容と費用の両面を比較検討することをおすすめします。
デイサービス(通所介護)は、自宅で生活する要介護者の方が日帰りで施設に通い、様々な支援を受けられる介護保険サービスです。このサービスは、利用者ご本人の生活を豊かにするだけでなく、介護するご家族の負担を軽減する上でも非常に重要な役割を担っています。
デイサービスで期待できる支援
デイサービスでは、主に以下の3つの側面から総合的な支援を提供します。
ご本人の自立支援と心身機能の維持向上
デイサービスの中心となるのが、ご本人の生活の質を高め、現在の能力を維持・向上させるための支援です。
日常生活動作 (ADL) の維持・改善: 食事や入浴、排泄など、日常生活に必要な動作の介助を通じて、現在の能力をできる限り維持できるようサポートします。例えば、入浴では介助を受けながらも自分でできることは自分で行うよう促し、自立を支援します。
機能訓練・リハビリテーション: 理学療法士や作業療法士といった専門職の指導のもと、個別の状態に合わせた機能訓練が行われます。これにより、筋力の維持や関節の可動域を広げ、転倒予防にもつながります。集団で行う体操なども、運動習慣の継続に役立ちます。
知的刺激と認知機能の維持: 塗り絵や計算ドリル、脳トレゲームなど、様々なレクリエーションを通じて、脳に適度な刺激を与え、認知機能の低下を緩やかにすることを目指します。
健康管理: 看護師が血圧や体温などのバイタルチェックを行い、体調の変化を早期に発見し、健康維持に努めます。

社会的孤立感の解消と交流の促進
自宅に閉じこもりがちになると、孤独感を感じやすくなります。デイサービスは、そうした気持ちを和らげ、社会とのつながりを感じられる場でもあります。
他者との交流: 同じ施設に通う他の利用者さんや職員との交流を通じて、会話が生まれ、笑顔が増えることで、精神的な活力が生まれます。
役割と居場所: 施設内での簡単な役割(例:配膳の手伝い、レクリエーションの準備など)を担うことで、社会とのつながりを感じ、生きがいを見つけるきっかけにもなります。
季節行事やイベント: お花見やクリスマス会など、季節ごとのイベントやレクリエーションに参加することで、季節の移ろいを肌で感じ、生活に彩りが生まれます。
ご家族の介護負担軽減
デイサービスは、介護するご家族の負担を軽減する上でも大きな役割を果たします。
介護からの休息: 日中、介護から離れる時間を持つことで、ご家族は心身を休めたり、自分の用事を済ませたりすることができます。これは、介護疲れによる共倒れを防ぐ上で非常に重要です。
情報交換や相談の場: 施設の職員やケアマネジャーとの定期的な面談を通じて、介護に関する悩みや不安を相談したり、情報交換をしたりすることができます。
介護技術のアドバイス: 施設で培われた専門的な介護技術や、認知症の方への接し方などについて、職員からアドバイスを受けることで、自宅での介護に役立てることができます。
医療体制との連携
デイサービスによっては、医療機関と連携して緊急時の対応体制を整えている場合もあります。利用中に体調が急変した場合でも、専門職が迅速に対応し、必要に応じて医療機関と連携して適切な処置を受けられる体制が整っています。
このように、デイサービスは利用者ご本人の自立支援と生活の質の向上、そしてご家族の介護負担軽減という、多角的な支援が期待できるサービスです。利用を検討される際は、ご本人やご家族のニーズに合った施設を選ぶことが大切です。
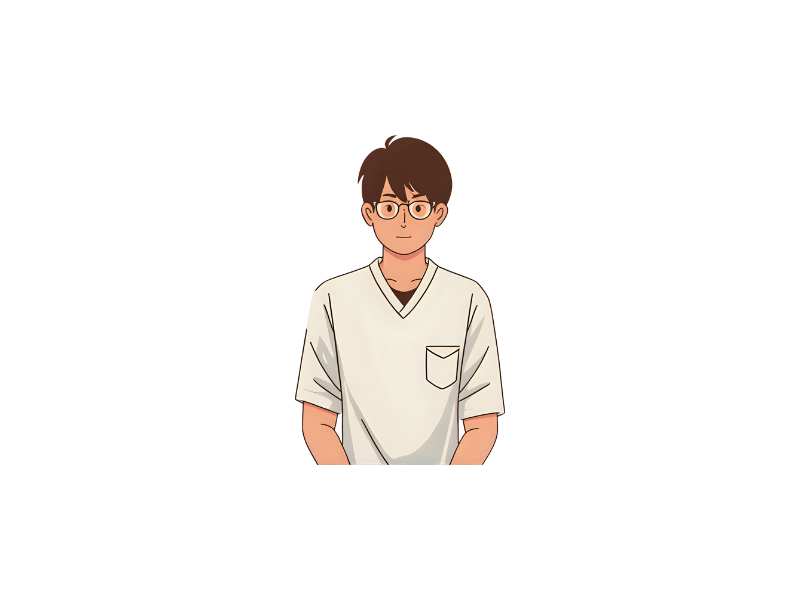
機能訓練の具体的な内容
デイサービスで行われる機能訓練は多岐にわたり、利用者の身体状況や目標に合わせて様々なメニューが提供されます。主な訓練内容は以下の通りです。
運動機能の訓練
筋力や柔軟性の維持・向上を目指します。
歩行訓練: 屋内や屋外での歩行練習、杖や歩行器を使った歩行訓練。
バランス訓練: 片足立ちや開眼片足立ちなど、転倒予防を目的とした訓練。
筋力トレーニング: 全身の筋力向上を目指すため、集団で行うラジオ体操や、マシンを使ったトレーニング、個別での筋力強化運動などがあります。
関節可動域訓練: 硬くなった関節を柔らかくする運動。
段差昇降訓練: 階段や段差を安全に昇り降りする練習。
口腔嚥下機能の訓練
口や喉の機能を保ち、誤嚥性肺炎の予防や食事を安全に楽しむための訓練です。
パタカラ体操: 「パ」「タ」「カ」「ラ」と発音することで、口周りの筋肉を鍛えます。
嚥下体操: 食事の前に声を出したり、舌を動かして唾液の分泌を促すなど、嚥下機能を高める体操。
認知機能の訓練
認知症の予防や認知機能の維持・向上を目的とします。
脳トレ: クイズ、パズル、計算問題など、頭を使うゲームを通じて脳を活性化させます。
回想法: 昔の出来事を語り合うことで、記憶を刺激し、精神的な安定を図ります。
手指を使った作業: ちぎり絵や折り紙、手芸など、手先を使った細かい作業は脳の活性化につながります。
日常生活動作(ADL)の訓練
日常生活で必要な動作をスムーズに行えるようにするための訓練です。
食事動作訓練: 箸やスプーンを上手に使う練習、食事の準備や片付け。
更衣訓練: 着替えの練習。
排泄動作訓練: トイレへの移動や着脱の練習。
入浴動作訓練: 入浴に関する一連の動作の練習。
応用的な動作訓練: 買い物、調理、公共交通機関の利用訓練など、より社会的な活動への参加を促す訓練も含まれます。
誰が機能訓練を行うのか
デイサービスで行われる機能訓練は、「機能訓練指導員」が担当します。機能訓練指導員は、利用者の要望や身体状況を把握し、「機能訓練計画書」を作成した上で、他のスタッフと協力しながら訓練を実施します。
利用するデイサービスを選ぶ際には、どのような機能訓練が提供されているか、また、機能訓練指導員やスタッフの体制・雰囲気がご本人に合っているかどうかも重要なポイントになります。見学や体験利用を通して、施設の実際の様子を確認することをおすすめします。