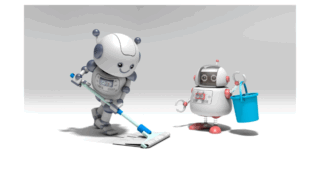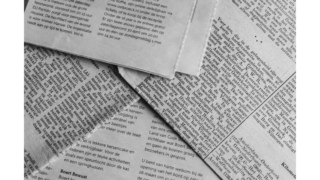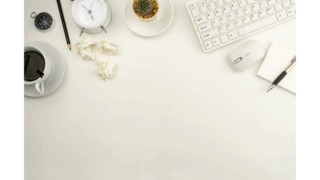介護老人福祉施設は、「特別養護老人ホーム(特養)」とも呼ばれ、介護保険法に基づいて運営される公的な高齢者施設です。寝たきりや認知症などで常に介護が必要で、自宅での生活が困難な高齢者のための「生活の場」として、手厚い介護サービスが提供されます。
介護老人福祉施設の概要
入居者が可能な限り在宅での生活に戻れることを目指しつつ、日常生活における支援、機能訓練、健康管理、療養上の世話などを提供します。長期入所を前提としているため、終身利用や看取りまで対応している施設も多いです。
主に地方自治体や社会福祉法人が運営しています。公的施設であるため、一般の民間施設と比較して費用を抑えられるというメリットがあります。
原則として、以下の条件を満たす65歳以上の方が入居できます。
要介護度3以上の認定を受けている方。
40歳〜64歳で、特定疾病が原因で要介護3以上の認定を受けている方。
例外的に、要介護1〜2の方でも特例入居が認められる場合があります。
日常生活の介護: 食事、入浴、排泄などの身体介護。
機能訓練: リハビリテーションなど。
健康管理: バイタルチェックなどの日常的な健康管理、療養上の世話。
相談援助、レクリエーション。
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」により、必要な職員の配置や設備が定められています。
医師: 入所者の健康管理や治療指導に必要な人数。
介護職員または看護職員: 入所者3人につき1人。ただし、夜間は看護師が常駐していない施設もあります。
生活相談員: 入所者100人につき1人。
栄養士または機能訓練指導員: 1人以上。
介護支援専門員(ケアマネージャー): 1人以上。
居室: 入所者1人あたり床面積10.65㎡以上。
医務室: 医療法に規定する診療所。
食堂および機能訓練室: 床面積は入所定員×3㎡以上。
廊下幅: 原則1.8m以上。
浴室: 要介護者が入浴するのに適した設備。
特別養護老人ホームとの違い
介護老人福祉施設と特別養護老人ホームは、法律上の根拠が異なりますが、基本的に同じ施設を指します。
介護老人福祉施設: 介護保険法に基づく名称。
特別養護老人ホーム: 老人福祉法に基づく名称。
入居対象者や提供されるサービス内容は同じです。
メリットとデメリット
メリット
費用が安い: 介護保険の補助や税制優遇があるため、民間の施設に比べて費用が抑えられます。入居一時金はありません。
24時間介護: 必要な介護を24時間受けられます。
長期入所が可能: 終身利用が可能で、退所期限は設けられていません。
倒産リスクが低い: 公的施設のため、運営が安定しています。
デメリット
入居条件が厳しい: 原則として要介護3以上でないと入居できません。
入居待ち期間が長い: 待機者が多いため、すぐに入居できないケースが多いです。
医療的ケアの限界: 常時の高度な医療ケアが必要な場合は、受け入れられないことがあります。
特養の入居条件の大原則
特養の入居条件は、主に以下の3つが原則とされています。
年齢: 65歳以上の高齢者であること。
要介護度: 介護保険の要介護認定で「要介護3」以上の認定を受けていること。
介護の必要性: 常時介護が必要であり、ご自宅での生活が困難であること。
ただし、40歳から64歳の方であっても、特定疾病が原因で要介護3以上の認定を受けている場合は対象となります。
要介護3とはどのような状態?
要介護3とは、食事や入浴などの日常生活動作において、ほぼ全面的に介護が必要な状態を指します。具体的には、一人での着替えが難しい、自力での立ち上がりや歩行が困難、入浴や排泄に手助けが必要、認知症の症状により目を離せない、といった状況が挙げられます。
特例入居が認められるケース
2015年の介護保険法改正により、原則として要介護3以上が入居条件となりましたが、やむを得ない事情がある場合には、要介護1または2の方でも特例として入居が認められることがあります。
特例入居となる具体的な例
以下のような状況にある場合、要介護1または2でも特例入居が考慮されることがあります。
認知症: 徘徊、暴言、暴力などの周辺症状が見られ、日常生活に著しい支障をきたしている場合。
知的・精神障害: 知的障害や精神障害により意思疎通が困難で、日常生活に著しい支障をきたしている場合。
虐待: 同居するご家族から身体的・心理的虐待を受けている疑いがあり、生命や心身の安全が脅かされている場合。
単身・介護力不足: 独居高齢者、または同居家族が要介護状態や重病などで介護力がなく、かつ地域の在宅サービスも不足している場合。
もし、ご自身やご家族が要介護1または2であっても上記の状況に当てはまる場合は、ケアマネジャーや特養の相談員に相談してみることをお勧めします。
入居申し込みの手続き
特養への入居手続きは、以下の流れで進めるのが一般的です。
必要書類の入手: 希望する施設から入居に必要な書類を入手します。
書類の準備: 入居申込書、介護保険証のコピーなどを準備します。自治体や施設によっては、介護認定調査票の写しや健康診断書が必要となることもあります。ケアマネが記載する欄がある場合もあります。
申し込み: 必要書類を揃えて、希望する施設に直接申し込みます。複数の施設を希望する場合は、施設ごとに申し込みが必要です。
地域密着型特別養護老人ホームの場合
「地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)」という種類もあります。これは、定員29名以下の小規模な特養で、原則として施設がある市区町村に住んでいる方のみが申し込めます。入居条件は通常の特養と同じですが、地域とのつながりを重視し、住み慣れた地域で生活を続けたい方に適しています。
特養は費用が比較的安く、24時間体制の介護を受けられるため人気が高く、入居までに時間がかかる場合があります。そのため、複数の施設に申し込みをして、ショートステイなどを利用しながら待機するのも一つの方法です。
特養は、介護が必要な方が24時間体制で介護を受けながら、安心して暮らせる「生活の場」です。入居者の方一人ひとりの生活スタイルを尊重しつつ、充実したサポートが受けられます。
特養での基本的な一日の流れ
特養での一日は、施設によって多少異なりますが、基本的なスケジュールは概ね共通しています。ここでは、神奈川県の地域密着型特別養護老人ホーム「クロスハート野七里・栄」の事例を参考に、一般的な一日の流れをご紹介します。
- 6時~7時起床
スタッフが声かけや誘導を行い、モーニングケア(着替え、洗顔、整髪など)を行います。ご自身でのケアが難しい場合は、介助を受けられます。
- 8時朝食
体調や移動が困難な場合を除き、食堂で他の入居者の方と一緒に食事をします。これはコミュニケーションの場としても大切です。食後には口腔ケアもしっかり行われます。
- 9時~12時体操や入浴など
体操は運動不足解消や血行促進になります。入浴は毎日ではなく、週に数回、決められた間隔で行われます。
- 12時昼食
朝食と同様に食堂で皆さんと一緒に食事をします。食事中の見守りも行われます。
- 14時頃レクリェーション
施設によって内容は様々ですが、体を動かすものや頭を使うものなど、楽しみながら行える活動が提供されます。
- 15時おやつ
昼食からの休憩時間として、おやつが提供されます。
- 18時夕食
- 20時就寝準備
- 21時消灯
このように、規則正しい生活リズムの中で、必要な介護を受けながら過ごすことができます。施設によっては、時間をきっちり決めず、入居者の方の状況や希望に合わせて柔軟に対応しているところもあります。

提供されるサービス
特養では、日常生活を送る上で必要な様々なサービスが提供されます。
身体介護: 食事、入浴、排泄、着替えなど、日常生活における身体的な介助。
生活支援: 居室の清掃や洗濯など、生活全般のサポート。
機能訓練: 身体機能の維持・向上のためのリハビリテーション。
健康管理: 日常的な健康チェックや、提携医療機関との連携による医療的なケア。
レクリエーション: 趣味活動や交流を促すためのイベントや行事。
看取り: 多くの特養では、終身利用を前提としており、看取りまで対応しています。
食事は、入居者の栄養状態や健康状態、嚥下機能、嗜好などを考慮して提供されます。アレルギーや糖尿病食などの特別な配慮が必要な場合も、施設と相談して対応してもらえます。外出や外泊などで食事を利用しなかった場合も、基本的に料金は変わりませんが、長期の外泊の場合は事前に連絡することで食費が発生しないようにできることもあります。
居室タイプと費用
特養にはいくつかの居室タイプがあり、それぞれ費用やプライバシーの確保の度合いが異なります。
多床室: 2人以上の相部屋タイプです。費用は最も抑えられますが、プライバシーは他のタイプと比較すると限られます。
従来型個室: 一人一部屋の個室タイプです。多床室よりもプライバシーが守られ、ユニット型よりも費用が安価な傾向にあります。
ユニット型個室: 10人程度の少人数を一つのユニットとし、それぞれが個室で、リビングなどの共有スペースも利用します。プライバシーが確保されつつ、他の入居者との交流も図りやすいのが特徴です。
ユニット型個室的多床室: 多床室を仕切りで個室のようにしたタイプです。個室に近いプライバシーと、共有スペースでの交流を両立できます。
居室の種類によって月の費用目安は異なり、要介護3の場合で、多床室が約8.8万円~9.7万円、従来型個室が約9.7万円~10.6万円、ユニット型個室的多床室が約11.5万円~12.3万円、ユニット型個室が約12.5万円~13.4万円となっています。
費用について
特養の月額費用は、主に「施設介護サービス費」、「食費」、「居住費」、「日常生活費」で構成されます。公的な施設であるため、入居一時金はかからず、民間の施設に比べて費用を抑えられるのが大きな特徴です。
施設介護サービス費: 介護度や居室タイプ、施設の職員配置などによって異なりますが、自己負担割合は1割(所得に応じて2〜3割)です。
食費・居住費: こちらは介護保険適用外で全額自己負担となりますが、所得に応じて「負担限度額認定」などの費用軽減制度が利用できます。
日常生活費: 医療費やレクリエーション費用、理美容費、嗜好品費などが含まれます。特養では、おむつ代や尿取りパッド代は施設側の負担となることが多いです。
国民年金のみを受給している方の場合、月額費用を年金だけで賄うのが難しいケースもありますが、高額介護サービス費や医療費控除などの減免制度を活用することで、経済的な負担を軽減することができます。
特養は高い人気があるため、入居待ちが長く、すぐに入居できない場合も多いですが、自宅での生活が困難な場合は、入居金が不要な有料老人ホームなどを一時的に利用する方法も考えられます。
待機期間の目安
特養の入居待ち期間は、施設や地域、個人の状況によって異なりますが、一般的には以下のようになっています。
全国平均: 大体2~3年が一般的とされています。厚生労働省の調査によると、2022年度時点で特養への入所待ちをしている方は、要介護3以上で25万3,000人、特例入所対象の要介護1・2の方で2万2,000人に上ります。
短期の場合: 早ければ1ヶ月以内に入居できるケースもありますが、稀です。
長期の場合: 3年以上かかることもあります。
待機期間が長い理由
費用の安さ: 公的施設であるため、費用が民間の施設に比べて安価である点が大きな理由です。入居一時金がかからず、月額費用も抑えられます。
終身利用: 終身にわたって介護を受けられるため、「終の棲家」として安定した環境を求める方にとって魅力的な選択肢です。
入居の優先順位
特養への入居は、申し込み順ではなく、その方の介護の必要性や緊急性が高い順に決まります。自治体ごとに独自の入所判定基準が設けられており、要介護度、認知症の状況、居宅介護サービスの利用状況、介護者の状況などが総合的に評価され、点数が高いほど入所優先順位が高くなります。
優先順位が高くなる要因の例
要介護度: 要介護度が高いほど優先されます。
認知症の状況: 日常生活に支障をきたすような症状が頻繁に見られる場合。
医療的ケアの必要性: 高度な医療的ケアが必要な場合。
介護者の状況: 介護者が不在、または介護が困難な状況にある場合。
虐待: 深刻な虐待が疑われる、または心身の安全確保が困難な状態の場合。
待機期間中にできること
特養の入居待ち期間中も、介護が必要な状態であれば在宅での生活を続けることになります。その間、以下のような対策を検討できます。
ショートステイの利用: 一時的に施設に宿泊し、介護や食事の提供を受けられるサービスです。定期的な利用で介護者の負担を軽減できます。
在宅介護サービスの利用: 訪問介護、デイサービス、訪問看護などを活用し、自宅で介護サービスを継続します。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用: 民間の施設は費用が高い傾向にありますが、入居待ちがほとんどなく、比較的早く入居できることが多いです。待機期間を一時的に過ごす場所として検討するのも良いでしょう。
早く入居するための工夫
複数の特養に申し込む: 複数の施設に申し込むことで、入居できる可能性が高まります。
希望エリアを広げる: 地域によって待機者の数や入所のしやすさが異なるため、入居希望エリアを広げることも有効です。
入居の必要性をアピール: 申し込み後も、要介護度や家庭状況(介護者の負担増など)に変化があった場合は、こまめに施設に報告することで、緊急性が上がり優先順位が早まる可能性があります。
ユニット型居室の検討: 相部屋の「従来型」に比べて費用は高くなりますが、個室の「ユニット型」は希望者が少ない場合があり、比較的早く入居できる可能性があります。
入所判定会議と基準
特養では、施設ごとに原則月1回「入所判定会議」が開催されます。この会議には、施設長、生活相談員、看護主任などの職員が参加し、各施設の入所判定基準に従って、入所希望者の緊急度や必要性を数値化して優先順位を決定します。
多くの自治体や施設では、入所判定基準表を作成しており、点数制で公平かつ透明性のある判断が行われるように努めています。
優先順位を決定する主な評価項目
特養の入所判定基準で評価される主な項目は以下の通りです。これらの項目を総合的に判断し、緊急度や必要性が高いと認められた方から入所できます。
本人の状況
要介護度: 要介護度が高いほど優先順位が高くなります。特に要介護3以上が原則の入所条件ですが、要介護度が4や5であれば、より高い点数が付与されます。
認知症の症状・行動障害の度合い: 認知症による徘徊、暴言、暴力などの行動障害が頻繁に見られ、日常生活に著しい支障をきたしている場合は、優先順位が高くなります。
医療的ケアの必要性: 痰の吸引、胃ろうなど、医療的なケアの頻度や管理の難しさも評価対象となります。
日常生活動作 (ADL) の状況: 食事、入浴、排泄、移動、着替えなど、身体介護の必要性が高いほど優先されます。
介護者の状況
介護者の有無や介護力: 主な介護者が高齢、未成年、または病気や障害がある、あるいは介護者が不在であるなど、家庭での十分な介護が困難な状況にある場合、優先順位が高くなります。
介護者の就労状況: 介護者が仕事を始めたことなどにより、介護が困難になった場合も緊急性が高いと判断されることがあります。
介護生活の長さ: 在宅介護生活が長いほど、介護負担の蓄積が考慮され、優先順位が上がる可能性があります。
在宅サービスの利用状況
居宅介護サービス利用率: 居宅介護サービスを限界まで利用しているにもかかわらず、在宅生活が困難な場合、優先順位が上がることがあります。ただし、病院や他の施設に入所中の場合は、在宅サービス利用率の評価が異なる場合があります。
住環境や経済状況
単身世帯・老老介護: 独居の方、または高齢者のみの世帯(老老介護)である場合、点数が高くなることがあります。
虐待の状況: 家族からの虐待や介護放棄、放置など、生命や心身の安全確保が困難な差し迫った状況にある場合は、最優先で入所が検討されます。
特例入所の判定基準
要介護1または2の方でも、以下のような「やむを得ない事情」がある場合は、「特例入所」として入所が認められることがあります。
認知症などによる行動障害: 認知症、知的障害、精神障害などにより、日常生活に支障をきたすような症状や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な場合。
深刻な虐待の疑い: 家族等による深刻な虐待が疑われるなど、心身の安全・安心の確保が困難な状態である場合。
家族からの支援がない: 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱であるなど、家族等からの支援が困難であり、地域の介護サービスも十分に受けられない場合。
特例入所の判断は、施設が入所判定会議で行いますが、市町村の適切な関与のもと、公正に行うこととされています。