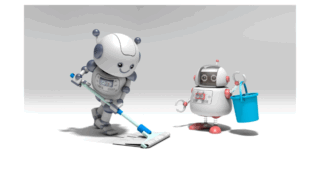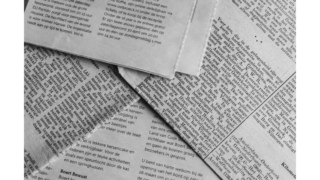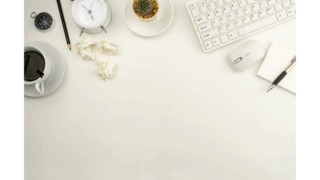脳血管疾患とは
脳血管疾患とは、脳の血管に異常が起きることで脳細胞が障害を受ける病気の総称です。脳の血管が詰まったり(虚血性脳卒中)、破れたりする(出血性脳卒中)ことで脳に障害が発生し、意識障害や片麻痺などの神経症状が現れるのが特徴です。突然発症することが多いため、「脳卒中」とも呼ばれています。
種類
脳血管疾患にはいくつかの種類がありますが、代表的なものは以下の3つです。
脳梗塞:脳の血管が詰まって血液が行き届かなくなり、脳細胞に異常が発生する状態です。血管が詰まる原因には、動脈硬化や心臓でできた血栓が脳の血管に流れてくることなどがあります。
アテローム血栓性脳梗塞: 動脈硬化で狭くなった血管に血栓ができて脳血管が詰まります。
ラクナ梗塞: 高血圧などによる動脈硬化で、脳の細い血管が詰まります。比較的小規模な梗塞で、自覚症状がない場合もあります。
心原性脳塞栓症: 心臓でできた血栓が脳の血管に運ばれて詰まることで発症します。大きな血栓が詰まることが多く、重症化しやすい傾向があります。
脳出血:脳の血管が破れて脳内に出血する状態です。
くも膜下出血:脳を覆う膜の中の「くも膜」と「軟膜」の間に出血が起こる状態です。脳動脈瘤の破裂が主な原因です。
これら以外にも、高血圧性脳症や脳血管性認知症なども脳血管疾患に含まれます。
脳血管疾患の男女比
脳梗塞と脳出血
脳梗塞や脳出血といった脳卒中全体では、男性の方が発症しやすい傾向にあります。厚生労働省の2020年の報告によると、脳卒中の新規発症者数は男性が約25万人、女性が約18万人で、男性が約3割多くなっています。
特に、若年層ではその差が顕著で、40歳未満の場合、男性の発症率は女性の2倍以上に及ぶとされています。しかし、加齢とともにこの男女差は縮小する傾向が見られます。
くも膜下出血
くも膜下出血に限って見ると、女性に多いという特徴があります。男性対女性の比率は3対7とされており、女性の方が圧倒的に多く発症しています。
女性特有のリスク要因
女性の場合、特定の要因が脳血管疾患のリスクに影響を与えます。
ホルモンの影響
閉経前の女性は、女性ホルモンであるエストロゲンの作用により血管が保護され、脳血管疾患のリスクが低い傾向にあります。エストロゲンは血管を拡張し、血栓の形成を抑制し、動脈硬化を防ぐ働きがあるためです。
しかし、閉経後はエストロゲンが大幅に減少するため、血管への保護効果が弱まり、脳梗塞の発症リスクが高まります。
その他のリスク要因
妊娠や出産、経口避妊薬の使用、ホルモン補充療法なども女性に特有の脳血管疾患の危険因子として挙げられます。また、片頭痛がある若年女性では、脳梗塞のリスクがわずかに増加する可能性も指摘されています。
若年層における性差
35歳以下の若年層では、女性の方が脳梗塞の発症率が高いという報告もあります。一般的なイメージとは異なり、35歳以下では女性の脳梗塞発症率が男性より44%高いという研究結果が示されています。
原因と危険因子
これらの要因が動脈硬化を進行させ、血管が傷ついたり、血栓ができやすくなったりすることで脳血管疾患のリスクが高まります。
症状
これらの症状は突然現れることが多く、一時的に改善しても脳梗塞の前触れである「一過性脳虚血発作」の場合もあるため注意が必要です。
予防
脳血管疾患を予防するには、原因となる生活習慣病の管理と健康的な生活習慣が大切です。
食生活の見直し: 塩分や脂質の摂取量を控え、栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。
運動習慣: ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を毎日30分程度行うことが推奨されています。
禁煙: 喫煙は脳血管疾患のリスクを大幅に高めるため、禁煙することが大切です。
定期的な健康診断: 特に高血圧や脂質異常症、心房細動などの持病がある場合は、定期的な検診と適切な治療が重要です。
脳血管疾患の治療法
脳血管疾患の最新治療法は、主に疾患の種類や病状の段階によって異なりますが、大きく分けて薬物療法、血管内治療、そして比較的新しい再生医療が注目されています。
薬物療法
特に脳梗塞の急性期には、血栓を溶かす薬が重要な役割を果たします。
tPA(組織型プラスミノゲンアクチベーター)静注療法:脳梗塞発症から4.5時間以内に点滴で投与することで、詰まった血栓を溶かし、血流を再開させる治療法です。この治療法により、脳梗塞の回復率が向上し、死亡率が減少したと報告されています。ただし、出血のリスクがあるため、適応には細心の注意が必要です。
血管内治療
細いカテーテルを血管に通して病変部を治療する方法で、開頭手術に比べて体への負担が少ないのが特徴です。
血栓回収療法:tPA療法で効果が見られない場合や、発症から4.5時間を超えていても8時間以内であれば、カテーテルを使って詰まった血栓を直接回収する治療法です。ステント型のリトリーバー(回収器)など新しいデバイスの登場により、再開通率が約8割まで向上しています。
脳動脈瘤コイル塞栓術:脳動脈瘤の中にプラチナ製の柔らかいコイルを詰めることで、動脈瘤への血流を遮断し、破裂を防ぐ治療法です。足の付け根などからカテーテルを挿入するため、開頭手術に比べて低侵襲です。
フローダイバーターステント治療:特に大型の脳動脈瘤に対して注目されている治療法で、網目の細かい特殊なステントを留置して動脈瘤内の血流を減らし、動脈瘤を血栓化させて破裂を防ぎます。正常血管内の金属量が少ないパルスライダーといった新しいデバイスも開発されています。
頚動脈ステント留置術:頚動脈の狭窄に対してステントという金属の筒を留置し、血管を広げて脳への血流を改善させる治療法です。粥腫の飛散を防ぐための回収装置も進化し、より安全に治療できるようになりました。
再生医療
これまで回復が難しいとされていた脳血管疾患の後遺症改善に期待が寄せられています。幹細胞を利用した治療法が中心です。
幹細胞治療:患者さん自身の脂肪などから採取した幹細胞を培養し、点滴などで投与することで、損傷した脳組織の修復や血管新生、神経再生を促します。これにより、麻痺やしびれ、歩行などの運動機能の改善や、脳卒中の再発予防にも効果が期待されています。現在、臨床研究が進められている段階ですが、今後、広く普及する可能性があります。
エクソソームを用いた治療:脳梗塞によってダメージを受けた脳組織の修復や神経再生を促進する新しい治療法として、細胞から分泌される微細な物質「エクソソーム」に注目した研究も進められています。
これらの治療は、早期に開始することが非常に重要であり、「タイム・イズ・ブレイン(時は脳なり)」という言葉があるように、発症からの時間が治療成績を大きく左右します。
脳血管疾患の予後
脳血管疾患の予後(病気の今後の見通し)は、疾患の種類、発症からの時間、治療開始のタイミング、損傷を受けた脳の部位、患者さんの年齢や健康状態、さらには生活習慣など、多くの要因によって大きく異なります。
脳血管疾患の予後を左右する要因
脳卒中の種類ごとの予後
脳血管疾患の中でも特に脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)は、症状や回復過程が異なります。
脳梗塞:血管が詰まるタイプで、発症から4.5時間以内でのt-PA(血栓溶解療法)使用が予後に大きく影響します。早期治療が成功すれば、後遺症が軽減される可能性があります。
脳出血:脳の血管が破れて出血するタイプで、出血量や場所によって予後が異なります。大量出血の場合は命に関わるリスクが高く、機能改善が難しい傾向がありますが、小さな出血の場合は時間とともに吸収され、後遺症が軽減することもあります。一般的に、脳梗塞よりも予後が悪く、後遺症に悩む人が少なくありません。
くも膜下出血:動脈瘤の破裂が主な原因で、手術後の血管れん縮(けいれん)によって二次的な脳梗塞のリスクがあり、慎重な経過観察が必要です。
早期治療の重要性
脳卒中は「時間との勝負」と言われるほど、発症から治療開始までの時間が予後に大きく影響します。特に脳梗塞では、発症後速やかに治療を開始することで、後遺症を軽減し、より良い回復が期待できます。
損傷部位と後遺症
脳のどの部分が損傷を受けたかによって、運動麻痺、感覚障害、言語障害、意識障害、認知機能障害など、さまざまな後遺症が現れます。同じ症状の患者さんは一人としていないと言えるほど、症状は多様です。
大脳皮質(前頭葉、側頭葉、後頭葉、頭頂葉)
前頭葉:意欲低下、判断力低下、感情コントロール障害。
側頭葉:記憶障害、言語理解の障害(ウェルニッケ失語)。
後頭葉:視野欠損、視覚認識の障害。
半身麻痺:脳の損傷部位の反対側に運動機能障害が見られるのが特徴です。いくつかの研究では右片麻痺の方がやや多いとされていますが、これは右利きの人が多く、体を支配する左脳の損傷リスクがわずかに高いためと考えられています。
年齢と健康状態
一般的に、高齢であるほど予後が悪い傾向にあります。また、高血圧、糖尿病、脂質異常症、不整脈などの基礎疾患や、喫煙、過度の飲酒といった生活習慣の乱れも予後を悪化させる要因となります。特に喫煙は、非喫煙者と比較して有意に予後不良となることが示されていますが、2年以上の禁煙でその負の影響が消失するという興味深い研究結果もあります。
リハビリテーションの重要性
脳血管疾患後のリハビリテーションは、後遺症の軽減や機能回復、そして社会復帰を目指す上で極めて重要です。脳は一度損傷を受けると再生能力が限られているため、リハビリテーションを通じて脳の「可塑性(かそせい)」と呼ばれる性質を利用し、残された脳機能や神経回路を最大限に活用・再構築することが目標となります。
リハビリテーションの目的と種類
脳血管疾患後のリハビリテーションは、急性期から回復期、維持期・生活期へと段階的に行われます。
急性期リハビリテーション
発症直後から早期に行うリハビリテーションです。
目的: 廃用症候群(寝たきりによる身体機能の低下)の予防、合併症の予防、早期離床を促し、回復期リハビリテーションへの移行を円滑にすることです。
内容: ベッド上での体位変換、関節可動域訓練、座位訓練など、無理のない範囲で早期から開始されます。発症後4.5時間以内に行われるt-PA静注療法などの急性期治療と並行して進められます。
回復期リハビリテーション
急性期治療を終え、容態が安定した段階で行われます。集中的なリハビリテーションにより、失われた機能の回復を目指します。
日常生活動作(ADL)能力の向上、自宅復帰や社会復帰に必要な身体機能の改善です。
理学療法(PT): 運動機能の回復、歩行訓練、バランス能力の改善などを行います。
作業療法(OT): 食事、着替え、入浴などの日常生活動作の練習や、手先の器用さ、高次脳機能の改善を目指します。
言語聴覚療法(ST): 発音・発声の練習、嚥下(えんげ)機能の訓練、コミュニケーション能力の改善を行います。
回復期リハビリテーション病院では、脳血管リハビリテーション料(I)の場合、1日あたり6〜9単位のリハビリテーションが行われ、約3ヶ月間の入院で約200万円程度の費用がかかることがあります。ただし、日本では医療保険制度があるため、患者さんの自己負担はその一部となります。
維持期・生活期リハビリテーション
回復期を過ぎ、自宅や地域に戻ってから行われるリハビリテーションです。
目的: 回復した機能の維持・向上、社会参加の促進、生活の質の向上です。
内容: デイケアや訪問リハビリテーション、自主トレーニングなど、個々の患者さんのニーズに合わせて継続的に行われます。
リハビリテーションの成功の鍵
早期開始: 「タイム・イズ・ブレイン」の原則通り、発症後できるだけ早くリハビリを開始することが、機能回復の可能性を高めます。
継続性: 脳の回復には時間がかかり、単発的なリハビリでは効果が限定されます。長期的に継続することが重要です。
患者さんの意欲と参加: 患者さん自身がリハビリテーションに積極的に参加し、目標を持って取り組むことが回復に大きく影響します。
家族のサポート: 家族の理解と協力は、患者さんのモチベーション維持や社会復帰に不可欠です。日本脳卒中協会が作成した「脳卒中克服十か条」でも、リハビリテーションの継続や社会参加の重要性が強調されています。
再生医療との組み合わせ
近年では、リハビリテーションだけでは改善が難しい後遺症に対して、再生医療(幹細胞治療など)を組み合わせることで、さらなる機能回復を目指す研究も進められています。幹細胞治療は、損傷した脳組織の修復や神経再生を促し、リハビリテーションの効果を高める可能性が期待されています。
生命予後
近年、予防医療の進歩や急性期の救命医療の充実により、脳血管疾患の死亡率は減少傾向にあります。しかし、年間約30万人が新たに脳卒中を発症し、そのうち多くの人が後遺症とともに人生を歩んでいます。介護が必要となる原因の第2位が脳血管疾患であり、特に要介護5においては第1位を占めています。 脳に損傷を受けた細胞は現状再生しないとされていますが、適切なリハビリと規則正しい生活によって脳の新しいネットワークを形成し、回復する可能性があります。ただし、回復の程度には個人差があります。
脳梗塞の再発率
脳梗塞は、一度発症すると再発のリスクが高く、1年以内に再発する割合は約10%と報告されています。さらに、発症後の累積再発率は、5年で約35%、10年で約50%にも達します。つまり、脳梗塞を経験した方の2人に1人は、10年以内に再発している計算になります。
タイプ別の再発率
脳梗塞にはいくつかのタイプがあり、それによって再発のリスクや、再発予防に使われる薬も異なります。
ラクナ梗塞:症状は軽いことが多いですが、再発を繰り返すとパーキンソン症候群や認知症の原因となることがあります。そのため、継続的な予防と適切な管理が非常に重要です。
脳卒中全体の再発率
脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の総称)全体で見た場合、年間再発率は約5%です。つまり、1年間で20人に1人の患者さんが脳卒中を再発すると言われています。
再発を招く要因
脳血管疾患が再発しやすい主な理由としては、以下のような危険因子をすでに持っている方が多いためと考えられています。
これらの危険因子を適切に管理することで、再発のリスクを大幅に減らすことができます。
年齢と再発率
脳梗塞の再発は、加齢とともにリスクが高まります。特に50歳以上は再発を繰り返す可能性が高いとされており、初発・再発ともに60歳以上の患者さんが全体の多くを占めています。
再発予防の重要性
脳血管疾患の再発は、初回発症時よりも重い後遺症が残ったり、命に関わったりする可能性があり、そのリスクは軽視できません。そのため、退院後の再発予防が非常に重要になります。
再発予防には、以下のような取り組みが推奨されています。
生活習慣の改善:禁煙、節酒、適切な食生活、運動習慣の確立など。
薬物療法:医師の指示に従って抗血栓薬(抗血小板薬や抗凝固薬)を継続して服用すること。特に心臓が原因の脳梗塞(心原性脳塞栓症)の場合は抗凝固薬が、それ以外の非心原性脳梗塞では抗血小板薬が推奨されます。
定期的な受診と検査:血圧や血糖、脂質、心房細動、頸動脈プラークなどを確認し、異常を早期に発見することが予後改善につながります。
再発予防のための薬剤は、脳梗塞の原因となった血栓がどこでできたかによって異なります。薬を正しく飲んでいたとしても、年間1〜2%の確率で脳梗塞が再発する可能性はありますが、継続的な服用によって再発率を低く抑えることができます。
食生活の改善
バランスの取れた食生活は、脳血管疾患の予防と再発防止に不可欠です。
塩分摂取の制限:塩分の摂り過ぎは高血圧の最大の原因の一つです。高血圧は脳血管疾患のリスクを高めるため、減塩を心がけましょう。高血圧患者では1日6g未満、成人男性は8g未満、女性は7g未満が推奨されています。
野菜や果物の積極的な摂取:野菜や果物には、脳血管疾患のリスクを低下させる効果があるという研究結果もあります。毎日5種類以上の野菜(1日350g以上)や果物を摂取しましょう。
適正なエネルギー摂取と腹八分目:肥満は動脈硬化を促進し、血栓ができやすくするなど、脳血管疾患のリスクを高めます。3食バランスよく食事を摂り、腹八分目を心がけることで、体重管理を行いましょう。
水分補給:水分不足は血液の粘度を高め、脳梗塞のリスクを増加させます。こまめな水分補給が重要です。
適度な運動習慣
適度な運動は、血行を改善し、コレステロール値を下げるなど、脳血管疾患の予防に寄与します。
有酸素運動:ウォーキング、ジョギング、早歩き、階段の上り下り、エアロバイクなどが推奨されます。特に、中程度の強度の有酸素運動を週に合計150分程度、または高強度の運動を週に2日以上、各20分程度行うことが効果的です。
身体活動量の増加:身体活動量が増加すると、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの脳梗塞の危険因子を発症しにくくしたり、改善させたりする効果があります。また、直接的に動脈硬化の予防にもつながります。
禁煙と節酒
喫煙と過度の飲酒は、脳血管疾患の主要な危険因子です。
禁煙:タバコは動脈硬化や血栓をできやすくし、脳卒中発症につながります。長年喫煙していたとしても、禁煙することで予防効果が期待でき、万が一発症した場合の重症度を下げられる可能性もあります。受動喫煙もリスクであるため、周囲の人のためにも禁煙は大切です。
節酒:アルコールは適量であればコレステロール値を下げる良い効果も期待できますが、飲み過ぎは体に負担をかけます。日本酒なら約1合、純アルコール量20g程度であれば、適量とされています。
定期的な健康管理
生活習慣病の適切な管理と定期的な健康チェックは、再発予防に不可欠です。
血圧管理:高血圧は脳卒中の最大の危険因子です。家庭での血圧測定を習慣にし、診察室での目安値140/90mmHg以上、家庭での目安値135/85mmHg以下を目標に管理しましょう。
血糖値、コレステロール値の管理:糖尿病や脂質異常症も脳血管疾患の危険因子です。これらを適切に管理し、治療薬を継続して服用することが大切です。
心臓病の治療:不整脈(特に心房細動)は、心臓内に血栓ができやすく、それが脳に運ばれて脳梗塞(心原性脳塞栓症)を引き起こすことがあります。不整脈などの症状がある場合は、早期に受診し適切な治療を受けましょう。
ストレス管理と質の良い睡眠:ストレスや疲労をためないようにし、十分な睡眠を確保することも、心身の健康維持に繋がり、結果的に脳血管疾患の予防に役立ちます。
これらの生活習慣の改善は、脳血管疾患が再発するリスクがあるためにも、一度脳卒中を経験した方だけでなく、予備軍の方にとっても非常に重要です。