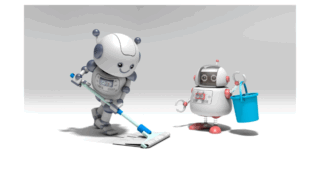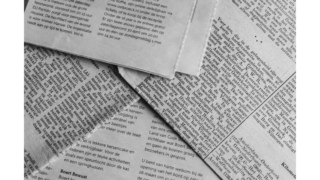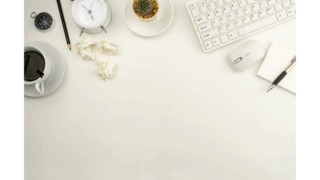要介護とは
日常生活上の動作を自分で行うことが困難で、何らかの介護を要する状態を「要介護」といいます。
介護が必要な人が、どのレベルに当てはまるか認定調査で見極めます。
要介護1~要介護5に区分されており、数が大きくなるにしたがって介護度は重くなり、より介護が必要な状態になります。
要支援よりも手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護を必要とする状態です。
時折、物事への理解の低下が見られ、混乱することがあります。
要介護1の状態に加えて、基本的日常生活動作についても部分的な介護を必要とする状態です。
例えば食事や排泄などで助けが必要になることがあります。
要介護2の状態と比べ、基本的日常生活動作、手段的日常生活動作を行う能力がともに著しく低下します。
家事などの身の回りのことや立ち上がり、歩行、排泄など、これまで助けがあれば自分でできていたことができなくなり、全面的な介護を必要とする状態です。
要介護3の状態に加えて、さらに日常生活動作能力が低下した状態です。
物事への理解も著しく、常に不安行動が見られます。
介護なしで日常生活を営むことは困難といえるでしょう。
要介護4の状態からさらに動作能力が低下し、助けがあっても全てのことにおいて自力でできない状態です。
要介護状態区分の中で最も重く、介護なしで日常生活を送ることはほぼ不可能といえます。
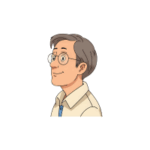
手段的日常生活動作って何だい?

掃除・洗濯・料理・買い物などの家事や交通機関の利用、電話の応対などのコミュニケーション、スケジュール調整、服薬管理、金銭管理、趣味などを指します
要支援とは
基本的日常生活動作をほぼ自分で行うことが可能で、現時点で介護が必要ではないけれども一部支援が必要な状態を「要支援」といいます。
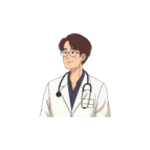
要支援は要介護よりも介護度は軽くなりますが、このまま年月を経ると要介護になることが予想される状態です。
要支援は要支援1と要支援2に分けられ、将来的に要介護状態になるおそれがある場合に認定される区分です。
要介護状態区分の中で最も軽く、ほとんど介護を必要としない状態です。
ただ自立(非該当)と異なるのは、日常生活の中の一部で見守りや支援が必要なところがある点です。
要支援1と同様にほとんど介護を必要とせず食事や排泄も自力で行えますが、要支援1と比べてより支援を必要とする状態です。
具体的には、立ち上がるときや片足で立つときなどに助けが必要だったり、移動(歩行)時に支えが必要だったりします。
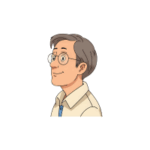
基本的日常生活動作って何だい?

日常生活における基本的な「起居動作・移乗・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容」動作のことを指します
区分支給限度額とは
要介護認定の区分ごとに、介護保険から給付される1か月あたりの利用上限額(区分支給限度額)が定められています。この限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の費用が全額自己負担となります。
区分支給限度額の目安(1か月あたり)
各要介護度における1か月あたりの区分支給限度額は以下の通りです。この金額は、サービス利用にかかる費用の10割分を示しています。
| 介護度 | 限度額 | 目安単位 |
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032単位 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531単位 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765単位 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705単位 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048単位 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938単位 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217単位 |
区分支給限度額は「単位」で表され、これを円に換算する際は、地域によって異なる1単位あたりの単価が適用されます。基本的に1単位=10円で計算されますが、人件費が高い地域では1単位が11.40円になる場合もあります。
支給限度額の範囲内でサービスを利用した場合、利用者の自己負担は所得に応じて1割、2割、または3割となります。
対象外となるサービス
以下のサービスは、区分支給限度額の対象外です
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護医療院
施設サービスは、施設内でサービスが完結するため、利用量を制限する必要がないとされています。
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して行う療養上の管理指導のことです。
居宅介護支援・介護予防支援
居住系サービス (短期利用を除く)
グループホームや特定施設などで、居住しながらケアを受けるサービス。
住宅改修費
手すりの設置や段差解消など、利用者の生涯につき上限20万円と定められており、区分支給限度額とは別の枠で管理されます。
認定調査あるある
認定調査員による訪問調査
市区町村の職員や委託を受けた調査員が自宅や施設を訪問し、身体機能や生活状況を聞き取ります。この際、普段の様子を見ている家族や介護者が立ち会うことが望ましいです。

初めまして。お名前と生年月日を教えてください。
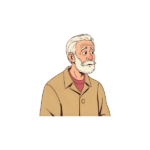
昭和12年3月5日丑年じゃ。

おいくつになられましたか?
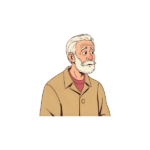
年?いくつだったけかな?75かな?

そうですか。今の季節はなんですか?春・夏・秋・冬のどれですか?
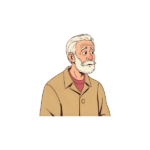
季節?季節ってなんじゃ。分からん。

では、今朝の朝ごはんは何を食べましたか?
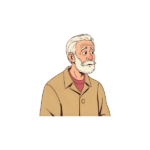
ごはん?何だったかな~?魚だったかな。

魚ですか。旬の魚いいですね。では、お体のことをお伺いしますね。トイレは自分で行ってますか?
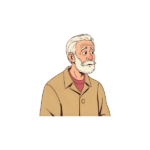
トイレ?トイレは行ってるに決まってるだろ。全部自分でやっとるわい。

ちょっと、いつも私が連れていってるじゃない。

そうですか。では、お着換えはご自身で選んで着ていますか?
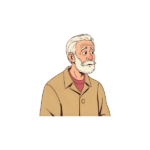
あたりまえじゃろ。なんでも自分でやっております。

ちょっと、調子に乗りすぎ・・

そうですか。では、お風呂に入る時は自分で体を洗ったり頭を洗ったりしていますか?
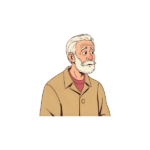
風呂?風呂はあんまり好きじゃないけど、自分でやらなきゃしょうがないだろ。自分で洗ってますよ。なんでそんな当たり前のこと聞くんじゃ。

はぁ~?何を言ってるの?全然違うんだけど・・

そうでしたか。すみません、お父さん。では、お父さんへの聞き取りは終わりです。あとは娘さんにお聞きしますね。
上記のケースのように、認定調査になると途端にシャキッとしてめちゃくちゃハッキリと答えることが出来たりします。高齢になっても社会性が残っている人が多く、一生を通してその能力は発揮されます。これまでの人生の知識と経験は深いところで形成され、他者への対応力や判断力、共感力へと繋がっているのだと感じます。
本人が「できる」と答えてしまったり、普段の状態より張り切って見せてしまうことはあるあるです。そうすると実際よりも低い判定となってしまったり、逆に大げさに手がかかっていると表現したりすると重く判定されることもあります。
特に、認知症の場合は正確な状況がつかみづらい傾向にあります。
そのため、家族が立ち会って、普段の困っている状況や介護の手間をより具体的に伝えることが非常に重要です。